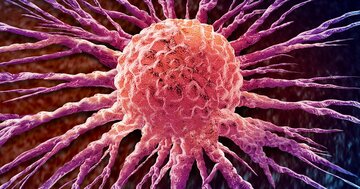写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
「○○を食べればor食べなければ健康になれる」――ちまたに流れる健康に関する数多の情報は、はたして本当に正しいのか。基礎医学・健康科学の専門家がタッグをくみ、世に広く流布する食事や運動に関する話題を取り上げ、科学的な根拠をもとにわかりやすく解説する。※本稿は、坪井貴司、寺田 新『よく聞く健康知識、どうなってるの?』(東京大学出版会)の一部を抜粋・編集したものです。
タンパク質の摂りすぎにも
デメリットがある
タンパク質を多く摂取することで骨格筋量が増加し、将来サルコペニア(編集部注/加齢によって筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下した状態)やフレイル(編集部注/加齢に伴い身体機能や認知機能、精神機能が低下し、要介護状態になるリスクが高まっている状態)になるのを防ぐことが期待できそうです。
しかしながら、私たちの健康状態は骨格筋量だけで決まるものではありません。それでは、タンパク質の摂取量とその他の生体機能との関係については、どのような研究結果が報告されているのでしょうか?
実は、タンパク質を多く含む食事は、糖尿病などを発症するリスクを増大させるという研究結果が報告されています。たとえば、ヨーロッパで約4万人を対象として行われた大規模調査では、炭水化物(糖質)もしくは脂質の摂取量を減らすかわりに、タンパク質の摂取量を増やす(タンパク質からのエネルギー摂取量を5パーセント程度多くする)ことで、2型糖尿病(編集部注/過食や運動不足などが原因で発症する糖尿病で、一般的に生活習慣病と称されるタイプのもの)の発症リスクが30パーセント増大するという結果が報告されています(注1)
(注1)Sluijs, I. et al., Diabetes Care, 33:43-48, 2010.