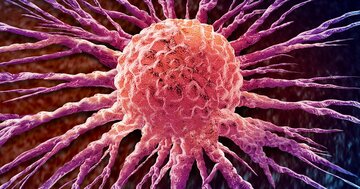カフェインは
神経を“興奮”させる
私たちの脳の中では、神経を興奮させる作用のある興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸や、逆に神経の興奮を鎮める作用のある抑制性神経伝達物質であるγアミノ酪酸(GABA)などが神経から分泌され、お互いに情報をやりとりしています。
神経だけでなく私たちの体内のすべての細胞は、糖を分解する過程でつくられるATP(アデノシン三リン酸)というエネルギー分子を用いて活動しています。一方、このATPが脳内で増えると、分解されてアデノシンという物質に変化します。
するとこのアデノシンが、神経に発現しているアデノシン受容体に結合し、神経細胞の興奮が抑えられます。その結果鎮痛作用や睡眠を引き起こしたりします。つまり、アデノシンは脳内で抑制性神経伝達物質として機能します。
カフェインの構造はこのアデノシンと非常に似ています。そのため、カフェインはアデノシン受容体に結合して、アデノシンの作用を抑制します。アデノシン受容体を鍵穴とすると、アデノシンは正しい鍵ですが、カフェインは、正しい鍵に非常に似せてつくった偽の鍵です。鍵穴には入るのですが、開錠することはできません。そのため、正しい鍵の仕事を邪魔します。
つまり、カフェインはアデノシンの神経の活動を鎮める作用を邪魔するため、神経は興奮するようになります。
人によってカフェインの
作用に違いが起こる理由
総合感冒薬の中には、鼻水や炎症症状を抑えるために配合されている抗ヒスタミン剤(ジフェンヒドラミン、マレイン酸クロルフェラミン、フマル酸クレマスチンなど)が眠気を引き起こすことがあります。
そこで、カフェインの神経興奮作用を逆手にとって、眠気予防や、疲労感の回復、軽減といった目的のためにカフェインが総合感冒薬に配合されています。
アデノシン受容体には、4種類(A1、A2A、A2B、A3)あります。それらの受容体は、運動調節、認知機能、感情、動機づけや学習などさまざまな機能を担っている大脳基底核にとくに多く発現しています(注4)。