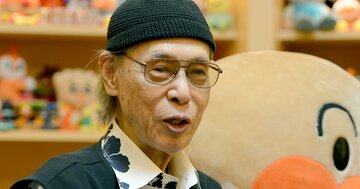実はその前に別の児童出版社から書き下ろしで「アンパンマン」を書いてみたのですが、編集方針と合わず、没になっていました。やなせたかしは原作のみで絵は別の巨匠に頼む企画でした。もし没になっていなかったら今のアンパンマンは存在していないかもしれません。
今度は違います。自分でストーリーも絵も全部つくることができる。だから、「ここぞとばかりにアンパンマンを描いた。幼児向けの絵本なので最初の1冊だけはひらがなの『あんぱんまん』でした」(『人生の歩き方 やなせたかし』)。
いまにも死にかけていた男を
自己犠牲で救うシリアス展開
幼児向けの絵本ですから、お腹のでた中年男を主人公にするわけにはいきません。どんなキャラクターにすべきか。メルヘン作家やなせたかしの創造力が羽ばたきます。
「このときはアンパンじたいが空を飛ぶほうが面白いと思って、アンパンを配るおじさんではなく、ヒーローの顔そのものをアンパンにして、困っている人に自分の顔を食べさせるようなストーリーにした」(同)
どんなヒーローにも、どんなキャラクターにも全く似ていないアンパンマンの独自性は「主人公の顔が食べ物で、交換できる」という点にありますが、「顔がアンパン」で「食べられる顔」で「取り替え可能な顔」という設定は、最初に確定していたのです。
また、やなせたかしは、『やさしいライオン』を絵本化したときと同様、幼稚園や保育園に通う幼児たちに向けた本にもかかわらず、「あんぱんまん」を子どもだけに向けた内容にしませんでした。
『あんぱんまん』の冒頭シーンを抜き出してみます。
「ひろい さばくの まんなかで、ひとりの たびびとが おなかが すいて、いまにも しにそうになっていました。そのとき、にしの そらから おおきな とりのようなものが、 ちかづいてくるのが みえました。」
ヒゲぼうぼうの痩せこけた大人の男が砂漠に倒れている。そんな中、夕日を背に現れたのが「あんぱんまん」。顔は現在のアンパンマンとほぼ同様ですが、3頭身ではなく、人間に近い背格好です。手もまんまるではなく、5本の指があります。衣装は茶色っぽく、マントはボロボロです。綺麗でもなく、可愛くもかっこ良くもない。