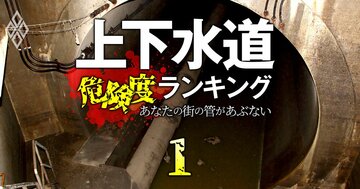写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
マンションの“終活”が問われる
改正区分所有法が来春施行
2026年4月1日、マンションの将来に関わる、ひとつの節目が訪れる。改正区分所有法の施行だ。
マンションの寿命は、「コンクリートは100年持つ」という言葉に代表される、物理的な頑健さで語られてきた。しかし、その前提である維持し続けること自体が、住民の高齢化や資金不足といった運営上の課題によって揺らいでいる。維持もできず、建て替えもままならない「出口のないマンション」は、もはや他人事ではない。
維持も建て替えもままならない状況に、「多数決による売却」など、管理組合が自らの手で将来を決めるための新たな選択肢をもたらすのが、今回の法改正だ。今、マンションの“終活”をどう設計するか、いわば経営的な判断がすべての管理組合に問われている。マンションの資産価値を守り抜くため、その戦略を具体的に考えるべき時代が来ているのだ。
維持も建て替えも限界に
マンションが抱える構造的問題
マンションの将来には、これまで2つの道があった。適切な維持管理を続けるか、それが困難な場合の建て替えである。しかし今、多くのマンションで、その両方の道が閉ざされようとしている。
まず維持管理の課題から見ていこう。
冒頭でも触れたように、マンションの寿命は「コンクリートが100年持つから大丈夫」という単純な話ではない。この数字は定期的な維持修繕を行っていくことが前提だが、その計画を滞りなく進める管理組合の力が、住民の高齢化と資金難によって衰えていく。結果、物理的には健全な建物が必要な修繕を受けられず、実質的な寿命を迎えてしまうのである。
では、建て替えはどうか。