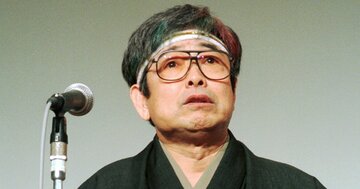写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
笑いは娯楽にとどまらず、文化であり教養でもある。明治大学文学部で教鞭をとる齋藤孝氏が、本来、日本人に備わっている笑いの感性を見つめ直す「視点」を説く。※本稿は、齋藤 孝『ユーモア力 現代社会に絶対必要な能力の鍛え方・磨き方』(山と溪谷社)の一部を抜粋・編集したものです。
聴衆が一緒になって爆笑
戦後復興時代の“笑い”
2024年、NHKラジオの『アナウンサー百年百話』という番組に出演し、ラジオ初期の日本人の笑いを知ることができました。
2025年3月はアナウンサー誕生から100周年にあたり、当時の最前線のアナウンサーの「ことば」をもとに放送100年を振り返るという番組です。
「日本で戦後復興を支えたバラエティ番組」として4回分収録し、その1つ『歌って当てる“3つの歌”』という番組は、有名な宮田輝アナウンサーが童謡「むすんでひらいて」を流し、音痴大歓迎ということで出場者が歌います。
ところがそのときの出場者は「むすんでひらいて」と歌わないで、最初から「ひらいて」「その手をにぎって」と歌ったので、宮田アナが「握るのはお寿司屋さんにまかせておきましょう」とツッコんで、みんなが爆笑しました。そういうラジオ番組です。その聴取率は64%だったそうです。会場には方言一つでも笑える温かい空気があって、宮田アナとのやり取りだけで笑いが起こります。
次に地方の女子高生が出てきて、緊張しているのか、宮田アナに「梅の花がきれいなところなんでしょ」と聞かれて「はぁ…」、「遠足なんかで行きましたか」と聞かれても「どこにですか」、「いや、梅の花の咲くところです」と宮田アナが言うと、女子高生は「いいや」とか言って話がうまく続かず、宮田アナが「おしゃべりするの好きなんでしょ」と聞くと、その女子高生は「はい」と言うわけです。それで宮田アナは「でも今晩は相手が悪いか」と、自分が面白くない男だから話してくれないんだなというふうにして、みんながワーッと笑ったんですね。丁寧なやり方で、品のいい笑いに持っていったのです。
また、『とんち教室』というラジオ初の国産クイズ番組がありました。
たとえば「今日は“ダイづくし”でお願いします」ということで、出演者たちはダイがつく言葉を言っていきます。もうほとんど大喜利大会です。
「持っておいでよ、その踏み台」「金があったわ、親父の代」
さらには、ダイがつけばいいということで「先生、そんなことイヤだい」でも笑う。