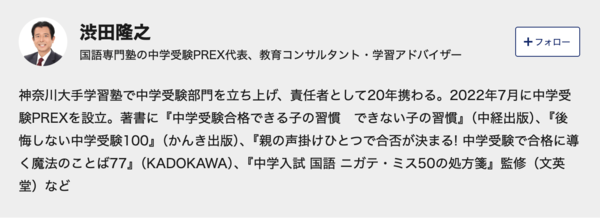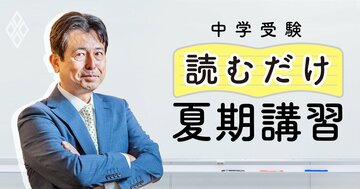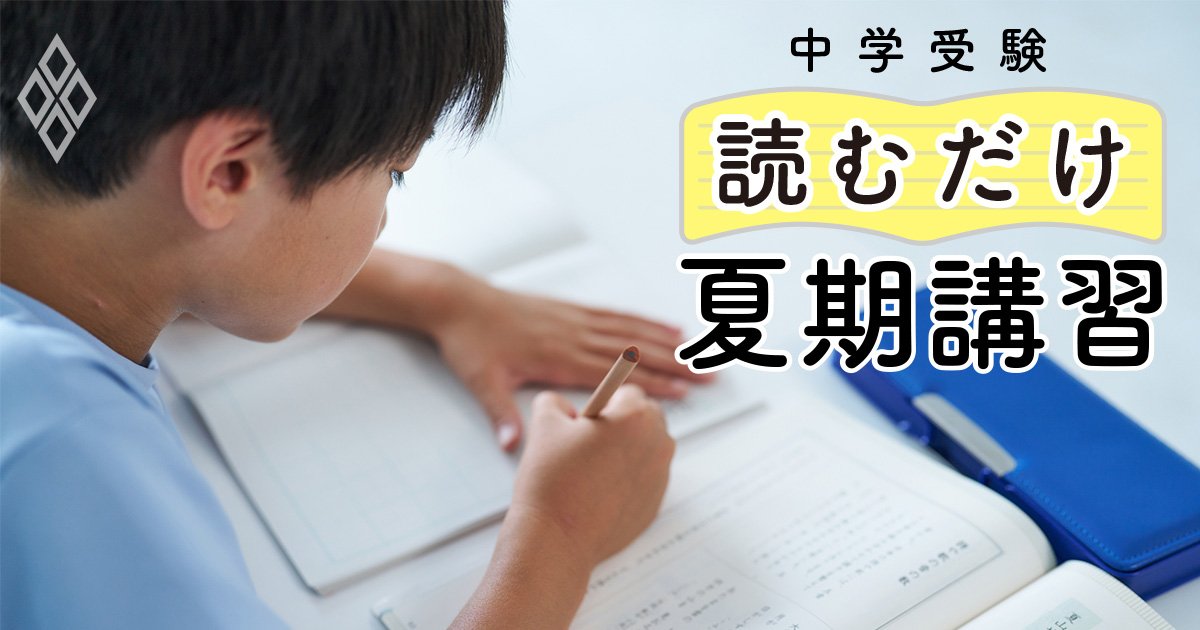 Key Visual by Ayumi Ogawa / Photo:PIXTA
Key Visual by Ayumi Ogawa / Photo:PIXTA
「夏期講習って、受けさせればそれでOKじゃないの…?」そう思っていると、もったいない! 実は、事前に“過去問”をチェックしておくだけで、講習の効果がぐんと上がるのです。第一志望校の傾向を知ってから臨むことで、夏の学びをより意味あるものに変えていきましょう。(国語専門塾の中学受験PREX代表、教育コンサルタント・学習アドバイザー 渋田隆之)
夏期講習の成功を左右する
大切な「下準備」とは?
計画的に学習に取り組めば、志望校との偏差値の差を埋めるには十分な時間が夏休みにはあります。塾は夏休みに行う夏期講習のことを「受験の天王山」と呼びますし、この時期の勉強のやり方によっては、9月以降の成績に大きく影響が出ることも事実です。
しかし、夏期講習を上手に生かせない場合は、時間と費用を無駄にしてしまいます。時には挽回不可能になることもあります。
前回の「夏期講習の失敗を防ぐ3つのポイント」続き、今回は「夏期講習を成功に繋げるために必要な下準備」として過去問の活用を紹介します。
受験校の過去問を見てから
夏期講習に参加しよう
過去問演習を始める時期は塾によってまちまちです。9月以降に解き始めるところが多いようで、塾や講師によっては夏前には「過去問を解くな」という指示が出ています。
しかし、私はこれには断固反対。夏休みから、もっといえば小学6年生になる春頃から「過去問の分析をした方が絶対に良い」と考えています。
なお、過去問を早期にやらない方針の塾は、ごく稀に生徒の中に「過去問対策をやれば、通常授業なんかやらなくても良い」と考えてしまうご家庭がいるのを危惧しての判断だと思います。この心配に対しては、私も賛成の立場です。
正しい活用をするという前提で、早い段階で過去問の分析をすることは、大きなアドバンテージにつながります。具体的にどこに目を向けることでどんなことが分かるのか、私の専門である「国語」の場合を挙げていきます。
(1)どんな形式の問題が多いのかわかる
記述が多い? 選択肢が多い? 抜き出し問題は何問くらい出るのか?
(2)どんな分野や範囲から出題されるのかわかる
韻文(詩や短歌俳句)は出る? 語句知識の難度や配点はどうなっている?
(3)文章量と問題数はどれくらいなのかわかる
何文字くらいの文章が出るの? (分量が多いということは)スピードが必要なの?
(4)年度により、出題形式そのものに大きな変化はあるのかわかる
毎年、同じような出題なの? 年によってガラリと変わることはあるの?
学校のホームページ等で過去問や解答、解説を公開しているところもありますが、そうでない場合は書店で過去問題集を買い求めることになります。出版社によっては、巻頭に傾向をまとめてあるので、まずはそちらを活用してみてください。
(4)で挙げた、「同じような形式の問題が繰り返し出るような傾向はあるのか?」について、開成中学など一部の学校を除いては、同じような形式で出題される学校がほとんどです。
あまり頻繁に形式を変えると、翌年の受験生の募集に影響が出ることと、もう一点は作問がやりにくいこと、入学する生徒の学力層が読みにくくなること、などが背景に挙げられます。逆に、大学付属校への転換や共学化などの大きな学校改革があった場合は、入試問題が大きく変わる可能性があります。
夏期講習で成功するためには、受け身でいるのではなく、少しでも主体的に授業に参加することが重要です。
第一志望の過去問のおおよその傾向を知ることで、「どこをどれぐらい頑張るべきか?」がわかり、それは大きな差になるでしょう。少なくとも、何となく授業に参加して、いつの間にか講習が終わっていたということはなくなります。