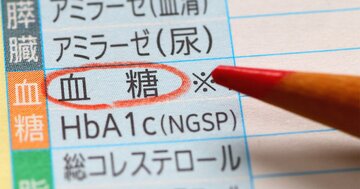しかし、老人性うつの場合、若い人に比べて心理的な症状の訴えは少なく、むしろ頭痛、腰痛、動悸(どうき)など身体の不調を訴えるケースが目立つことが特徴。それらの症状に加えて、不眠や食欲減退は「年のせい」と見過ごされがちです。
老人性うつの症状は、認知症とも似ていて、「風呂に入らない」「物忘れが多い」といった変化は、いずれにも見られます。実際、認知症を疑って受診し、うつの診断を受ける人も。
われわれ専門医が、認知症と老人性うつを見分けるポイントは、「いつ症状が始まったか」です。
認知症の場合は、「おそらく2~3年前」などはっきりしないことが多いのですが、「今年の春から」「昨年のクリスマスを境に」など、本人や家族が発症の時期をはっきり把握している場合は、うつの可能性が高い。短い期間にさまざまな症状が表れるのがうつの特徴です。
老人性うつは
早期治療で8割回復
また、うつの人は、自分を責めたり罪悪感を覚えたりして、とてもつらそう。中期以降の認知症の人はニコニコしていることが多く、大きく違う点です。
さらに私が診察で聞くのは、食欲と睡眠について。「食欲減退」と「早朝覚醒(明け方に目が覚める)」の2つが揃ったら、うつを疑います。
認知症と違って、老人性うつは適切な治療によって治る病気です。そのため、早期発見・治療が何より大切。
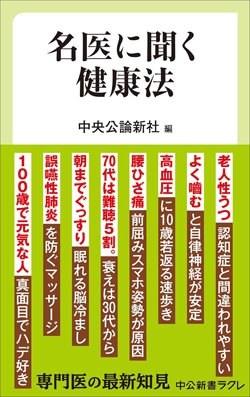 『名医に聞く健康法』(中央公論新社編、中央公論新社)
『名医に聞く健康法』(中央公論新社編、中央公論新社)
というのも、うつの進行によりセロトニンが足りない状態が続くと、脳内の神経が傷んで回復が難しくなるからです。ですから、変化に気づいたら早めに精神科を受診しましょう。問診に時間をかけ、症状をきちんと聞いてくれる良い医者を見極めてください。
老人性うつの治療の基本は薬物療法です。早期であれば8割くらいの患者さんは抗うつ剤で治ります。1年ほどで症状が安定するでしょう。
ただ、うつは再発しやすい病気なので、もともとセロトニンが少ない高齢者の場合は、治っても少量の薬を飲み続けるのが原則です。なお、認知症と老人性うつを併発する人もいますが、両方の薬を同時に服用しても問題はありません。
老人性うつの患者は、温かい目で見守ることが大切です。精神状態が悪いときは休養第一ですが、改善してきたら、少しずつ役割を与えるのが良策。自分が「役に立っている」という思いは、心の回復につながります。