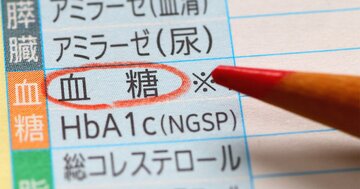写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
高齢者がかかる2つの脳の病、「認知症」と「老人性うつ」は、初期症状が似ていて見分けるのが難しく、医者でさえ誤診することがあるという。和田秀樹医師が、早期発見のポイント、治療法、予防法を詳しく解説する。※本稿は、中央公論新社 編『名医に聞く健康法』(中央公論新社)の一部を抜粋・編集したものです。
見分けるのが難しい
「認知症」と「老人性うつ」
年を重ねれば、ほかの臓器と同じように脳も衰えていきます。超高齢社会において、脳の老化現象である「認知症」が増加するのは必然といえるでしょう。厚生労働省によると、65歳以上の認知症患者数は2020年で630万人、25年には730万人になると予測されています。
実は、同じく脳に起因する病気で多いのが「老人性うつ」です。65歳以上の高齢者のうつ病発症率は若い人よりも高く、抑うつ気分の人も含めれば300万人はいると私は推測しています。
高齢者の人口が3640万人(2021年)であることから、患者数の多さがおわかりいただけるのではないでしょうか。70歳を過ぎたら、この2つの脳の病に見舞われる可能性が少なくない。どう防ぎ、どう乗り越えるかが、高齢期を幸せに過ごすための鍵になってきます。
そもそも、認知症と老人性うつは、まったく違う病気で、治療も対処法も異なるのですが、あまり知られていません。「なんとなく元気がなく、1日中ボーッとしている」といった初期症状が似ていて見分けるのが難しく、医者でさえ誤診することがあるほどです。