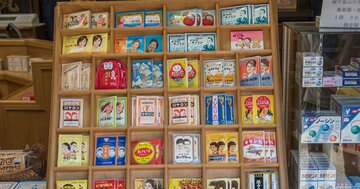ケロリン桶が持つ
「庶民文化」の味わい
銭湯ってやっぱり健康に近い。薬のケロリンと銭湯のケロリン桶っていうのもまたいい距離感なんです。持ちつ持たれつというか。昔も今も変わらずに置いてあるものがあるんです。
例えば体重計。デジタルでない目盛りの針が動くレトロなものが結構ありますね。ケロリン桶もそうですが、昔からあるものを見ていると、時代背景を含めて豊かな気分を感じさせてくれるんです。その感覚を若い人たちにも知ってほしい。
あまりにも身近すぎるものの良さっていうのは、なかなか気づかないんです。でも銭湯の空間に溶け込んでいるケロリン桶の奥深い味わいというのは、まさしく「庶民文化」なんですね。
町田 忍/庶民文化研究家。1950年東京都出身。和光大学人文学部芸術学科卒業。学生時代にヨーロッパを一人旅。その後、警視庁警察官を経て、江戸から戦後にかけての庶民文化・風俗を研究のため独立。『町田忍の懐かしの昭和家電百科』『町田忍の銭湯パラダイス』など著書多数。
壇蜜が語る
サウナ通いのきっかけ
最初にサウナに入ったのは、7年前くらいでした。実家の裏の銭湯にサウナが付いていて、それで試しに入ってみようかなって。久々に銭湯に行ってみると、ご主人も奥様も皆さんお変わりなく、なにか落ち着く場所だなって思っているうちに、いろんな方と知り合って。そうしているうちに、どんどんサウナが好きになって行く回数が増えてきた感じですね。
サウナに入っているときの自分の中の決めごとは、高い温度の場所に居座りすぎないということでしょうか。たとえばいちばん上の段は、高温なので汗がダダーッと流れるんですけど、むしろ中段とか下段のところでじっくりと汗を流して「むくみが取れた」とか実感が欲しいんですよね。温度でいうと、だいたい85℃ぐらいでしょうか。
入っている時間については、その日のコンディションによるので何とも言えないんです。平均すると12~13分くらい。サウナに置いてある12分計はちゃんと見てますけれど、何分まで頑張るとかいうプレッシャーにならないようにしています。