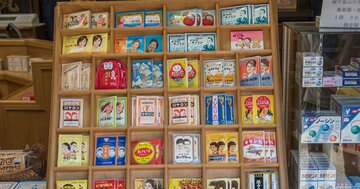Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
今やお馴染みとなった、黄色いプラスチックの「ケロリン桶」。これはもともと富山の内外薬品商会が、自社の解熱鎮痛薬・ケロリンの広告戦略として世に放ったものだ。その誕生の中心には、内外薬品商会を経営する笹山家に婿入りした笹山忠松と、広告付き桶を発案した山浦和明の存在があった――。※本稿は、監修・笹山敬輔『ケロリン百年物語』(文藝春秋)の一部を抜粋・編集したものです。
結婚を機にお寺の子から
内外薬品商会へ
忠松は大正15(1926)年、金沢市の少林寺に中野家の次男として生まれました。少林寺は現在の片町に近い伝馬町にあり、兄の松禅とともにそばを流れる犀川でよく遊び、川向かいの子らとしょっちゅう喧嘩していました。
しかし、さすがに寺育ちのせいか慈悲の心をもち、戦後、犀川の新橋の下に住む貧しい人たちのために、家から鍋を持ち出して食べさせていたそうです。そんな性格を見抜いていた兄は、弟は寺に向くと考え、仏教系の駒澤大学への入学を勧めました。
しかし、忠松は終戦直後のキャンパスで自由を謳歌します。学徒出陣から帰って復学した兄が目にしたのは、大学祭の壇上でピカピカの帽子をかぶり、応援団長よろしく声を張り上げている弟の姿でした。
そして、兄より一足先に卒業した忠松は僧籍に入らず、金沢市役所に就職しました。思いがはずれた兄とともに、もう1人、この就職を心配していた人がいます。笹山ハル(編集部注/経営破綻に陥っていた内外薬品を立て直した、笹山林蔵の後妻)は、孫娘の慶子のことを思ってやきもきしていました。