そもそも窒素は空気中に約80%も含まれていて、液化する温度も絶対温度77度(摂氏マイナス196度)と比較的高温で扱いやすいのです。この液体窒素の温度以上で超伝導となる物質があれば、その応用範囲は一気に広がることになります。
そして、このとき発見された超伝導体の温度は絶対温度93度だったのです。
高温超伝導フィーバーに
世界中が躍る
実はこの発見の布石ともいうべき発見が、前年の6月にありました。それはIBMチューリッヒ研究所の物理学者ヨハネス・べドノルツとアレクサンダー・ミュラーによる、絶対温度35度で超伝導体となる物質の発見です。温度自体は高くないのですが、その物質は金属ではなく電気を通さない「銅酸化物」という絶縁体でした。
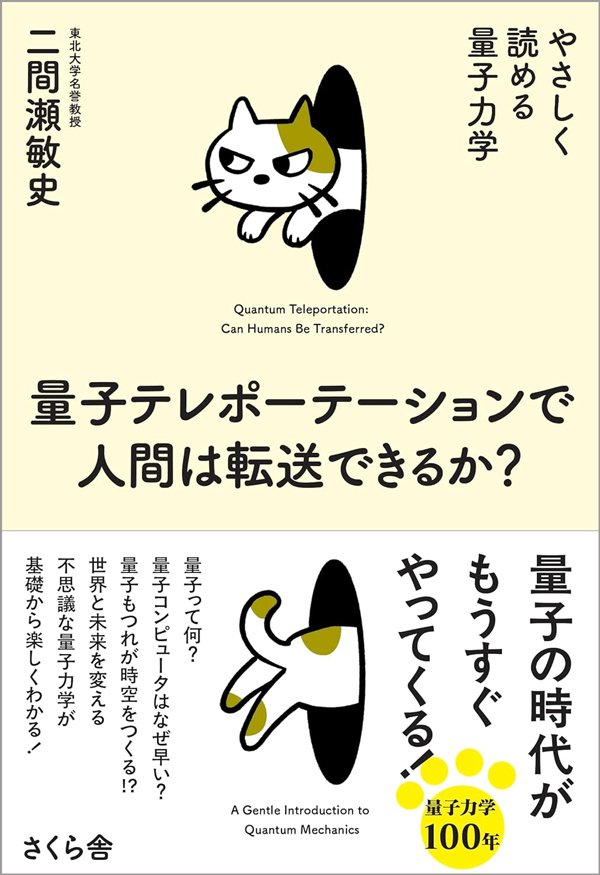 『量子テレポーテーションで人間は転送できるか?やさしく読める量子力学』(二間瀬敏史、さくら舎)
『量子テレポーテーションで人間は転送できるか?やさしく読める量子力学』(二間瀬敏史、さくら舎)
彼らは銅と酸素からできた結晶にランタンやバリウムを注入したときの変化を調べており、その過程で注入した原子の影響で、結晶中の銅原子の電子がはぎとられ、自由電子となり、絶対温度35度で超伝導となる可能性を指摘したのです。
彼らの発表の数ヵ月後には、日本のグループがマイスナー効果を確認して、実際に彼らの発見した物質が超伝導体であることを示しました。ここから、高温超伝導フィーバーと呼ばれる状態が数年間続き、世界中で競争心むき出しの競争となります。
1987年2月には絶対温度90度で超伝導となる銅酸化物が発見され、1993年頃までには絶対温度135度が達成され、大気圧の下での最高温度となっています。また銅酸化物以外に、鉄酸化物や硫化水素などの水素の化合物といった違う素材でも超伝導が起こることが確認されており、大気圧の100万倍という超高圧では絶対温度294度(摂氏21度)という超伝導体も発見されています。







