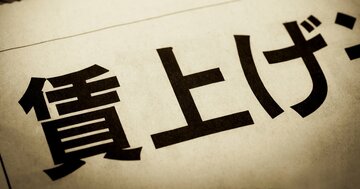2024年7月、最高値をマークした日経平均株価 Photo:PIXTA
2024年7月、最高値をマークした日経平均株価 Photo:PIXTA
近年、日経平均株価は3~4万円台の高値をキープし、一時はバブル期に記録した最高値も更新した。その一方で、米をはじめとする様々な物価高もあって、庶民の生活は厳しいまま。なぜ、株価は高いのに、庶民にはその恩恵が届いていないのか。第一生命経済研究所済調査部主任エコノミスト・藤代宏一氏の新刊『株高不況 株価は高いのに生活が厳しい本当の理由』(青春出版社刊)から、抜粋して紹介します。
景気回復の実感に乏しい株高
2024年3月に日経平均株価は4万円の大台に乗せ、同年7月には最高値を更新、現在も高値を維持しています。もっとも、街角からは「景気が良くないのに株価ばかり上がっている」という声が多く聞かれました。
一方、筆者を含む多くの専門家は「株価上昇は実体を伴っている。バブルではない」という解説をしました。いったいどちらが正しいのでしょうか。
日常的に経済指標に囲まれている筆者のような特殊な立場からすれば、「現在の株価は企業収益に対して適正と言える範囲内であり、1989年のバブル期との違いは明白」と比較的強い根拠を持って株価上昇の背景を整理することができましたが、そうでない方からすれば、景気回復の実感に乏しい中で進む株高に違和感を覚えたと思われます。
日経平均株価が4万円に迫った1989年当時、筆者はまだ小学生だったため、当時の実情を知る由もないのですが、会社の先輩などから、日本人は競うように贅沢をしていたと聞いています。それに対して現在は、そうした雰囲気をほとんど感じません。むしろ、食料品やガソリン価格の上昇をどう乗り切ったらいいかなど、生活防衛的な話題に囲まれている印象です。