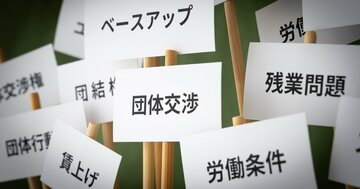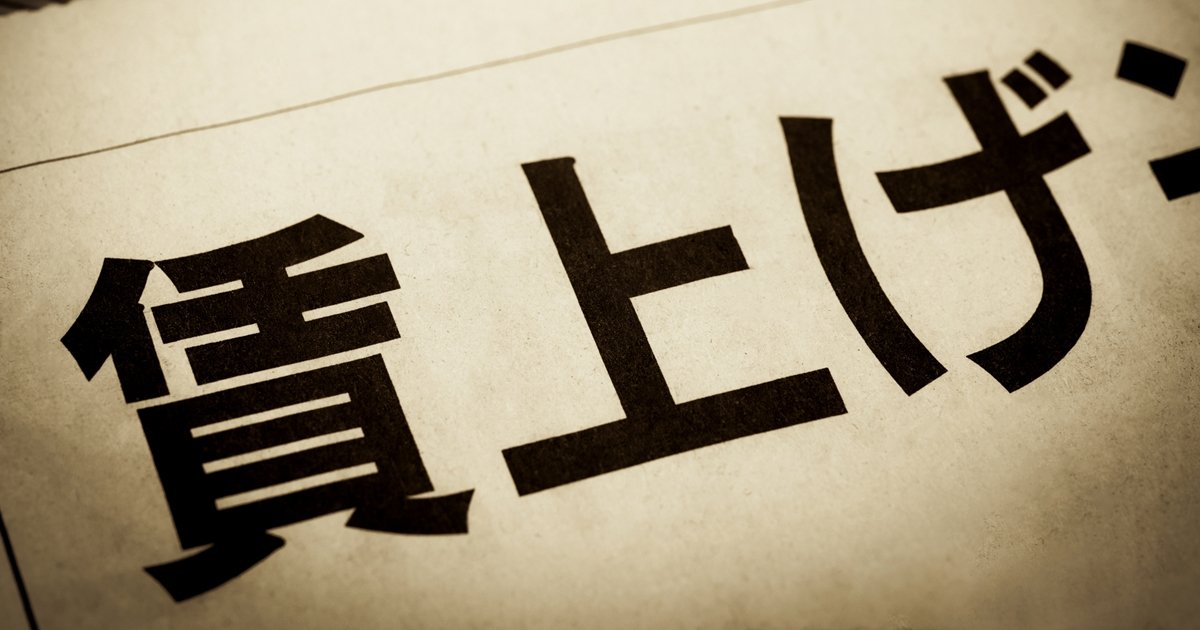 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
春闘の平均賃上げ率が5.46%となり、景気回復への期待が高まっている。しかし実態は、大企業が強い立場を利用して価格を引き上げ、消費者から利益を得ているに過ぎない。賃上げされない中小企業の労働者がその負担を担っており、これは「好循環」ではなく負の循環である。※本稿は野口悠紀雄『日銀の限界 円安、物価、賃金はどうなる?』(幻冬舎新書)の一部を抜粋・編集したものです。
輸入物価が下落しても還元せず
賃上げでさらなる価格転嫁
まず、世界的なインフレと円安によって、輸入物価が上昇した。これが消費者物価を引き上げた。このような動きが、2022年から23年にかけて生じた。23年に春闘の賃上げ率が高まり、賃金が上昇し始めた。しかし、物価上昇率のほうが高いので、実質賃金は下落を続けた。
以上が第1段階だ。ここまでは、アメリカのインフレに端を発した玉突き的な変化だ。日本から見ると、コストプッシュ・インフレだ。
それは、国民生活を貧しくするという意味で大問題だが、経済メカニズムとしては理解しやすい。企業は、原材料価格の高騰分を販売価格に転嫁する。これは、これまでも行なわれてきたことであり、日本の消費者物価はそれによって上昇した。
今回は輸入物価の上昇率が非常に著しかったために、完全に転嫁できるかどうかが、当初は疑問視されていた。しかし、実際には、原価上昇分をほとんど消費者物価に転嫁できた。大企業は取引上、優位な立場にあるので、ほぼ完全に転嫁できただろう。このため、企業の粗利益(売り上げ―原価。なお、これは付加価値にほぼ等しい)が増えて、賃上げが可能になった。
ところが、2022年の10〜12月期頃から、状況が変化した。世界的な物価高騰が収まったために、輸入物価が低下し始めたのだ。それにもかかわらず、国内物価は上昇を続けた。これが第2段階だ。