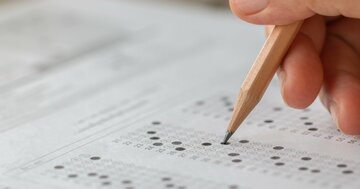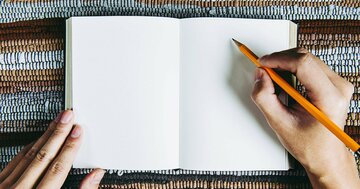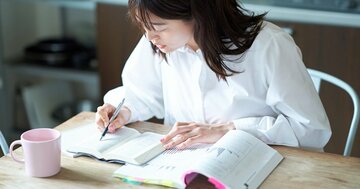宅建合格した人が「7月に勉強していたこと」【今からでも大丈夫】
働きながら3年で、9つの資格に独学合格! 大量に覚えて、絶対忘れないノウハウとは?
「忘れる前に思い出す」最強のしくみ、「大量記憶表」を公開!
本連載の著者は棚田健大郎氏。1年間必死に勉強したにもかかわらず、宅建試験に落ちたことをきっかけに、「自分のように勉強が苦手な人向けの方法を編み出そう」と一念発起。苦労の末に「勉強することを小分けにし、計画的に復習する」しくみ、大量記憶表を発明します。棚田氏の勉強メソッドをまとめた書籍、『大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法』の刊行を記念して、メソッドの一部を公開します。
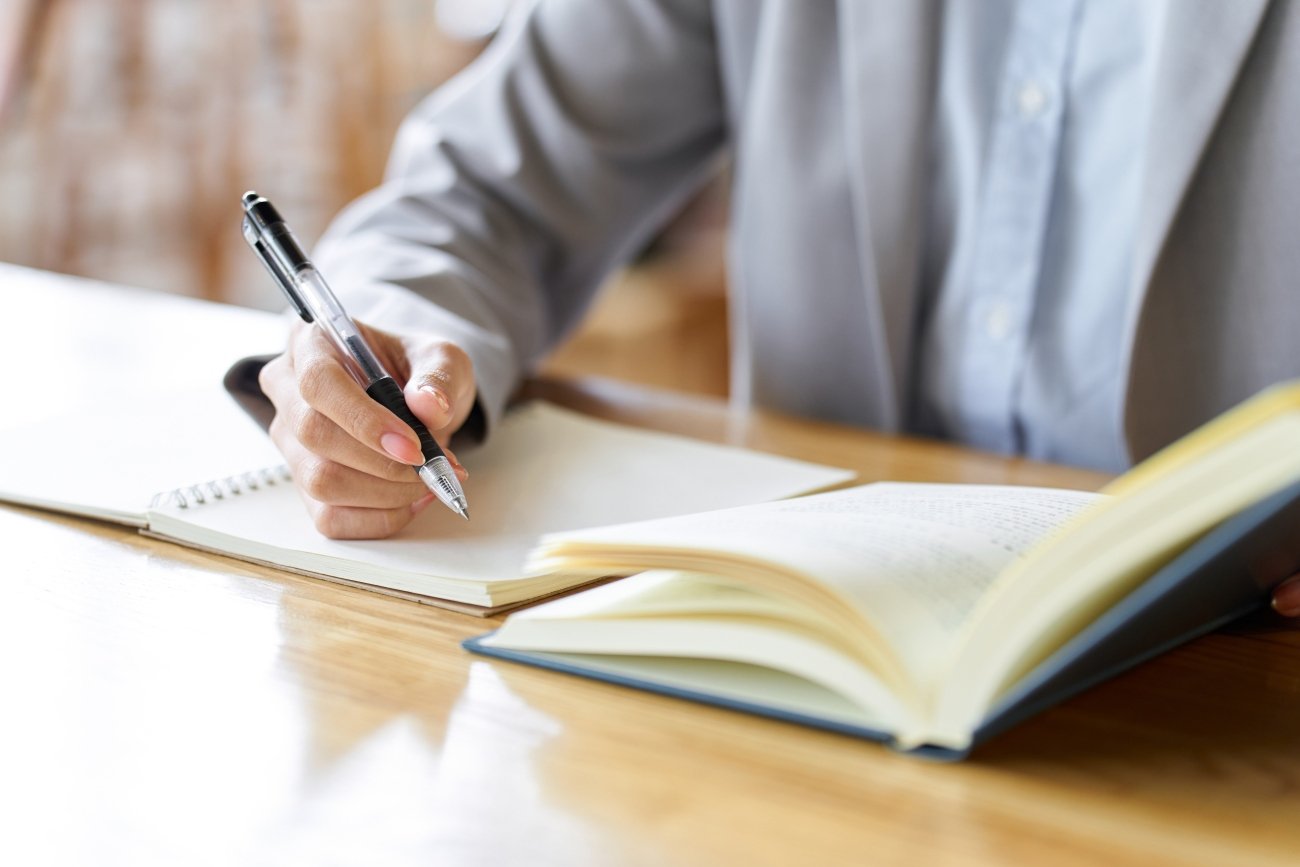 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
7月に何を勉強すればいいのか?
宅建試験の出願も始まり、いよいよ本番までのカウントダウンが本格化してきました。多くの受験生にとって7月は学習の正念場。ここでの取り組み方が、10月の合否を大きく左右します。
本日は、現時点での学習の進捗状況に応じて、7月以降どのように学習を進めるべきかを、私自身の経験に基づいてお話ししていきます。皆さんの状態も、おそらく次のいずれかに当てはまるのではないでしょうか。「すでに全分野の学習が一通り終わっている人」「宅建業法と法令上の制限は終わっている人」「どちらか一方だけ終わっている人」「ほとんど手をつけられていない人」。どの立場にあるかによって、これからの戦略は大きく変わります。
勉強が順調な人は「これ」をやろう!
すでに全分野を一周終えている人は、素晴らしいペースで学習が進んでいると言えます。ただし、ここで気を抜いてはいけません。覚えた知識は、想像以上に早く抜け落ちていきます。重要なのは、“忘れないための学習”へと切り替えることです。制覇した問題集は、大量記憶法で管理し、最低でも2週間に1回、可能であれば週1回の頻度で「思い出す」作業を行いましょう。大量記憶法とは、「忘れる前に思い出す」勉強法で、大量記憶表というシートを活用します。
このタイミングは人によって異なるので、自分の記憶の維持に最適なペースを見つけることがポイントです。また、模試を活用して理解度をチェックするのも大切です。結果が振るわなくても落ち込む必要はありません。市販の模試は出題傾向が本試験と異なることが多く、あくまで現時点での理解度を測る道具と考えてください。もし点数が思ったより低かった場合は、答えの理由まで掘り下げて、自分で解説に周辺知識を書き加えるなどして、知識を補強していきましょう。
宅建業法と法令上の制限が終わった人は「これ」をやろう!
宅建業法と法令上の制限が終わった人は、いま最も多い層かもしれません。この場合、次に着手すべきは権利関係ですが、既習分野の記憶を保つことも忘れてはいけません。宅建業法と法令の復習を週1~2回の頻度で同時並行しながら、権利関係を進めていきましょう。お盆前までに権利関係を終わらせるのが一つの目安です。完璧を目指すと時間が足りなくなるので、まずは最後まで終えることを優先し、仕上げる形で構いません。このフェーズまで到達すれば、模試にも本格的に取り組むことができ、自分の解答スピードや時間配分の課題にも気づけるようになります。
宅建業法か、法令上の制限、どちらかしか終わってない人は、「これ」をやろう!
一方で、宅建業法か法令上の制限のどちらか一方しか終わっていない人は、7月と8月を使って残りの分野と権利関係を一気に終わらせましょう。特に宅建業法は得点源ですので、まだ終わっていないなら最優先です。この段階の学習では、未修分野の学習と並行して、終わった分野の復習も続ける必要があります。権利関係を最後に持ってくることで、業法と法令を確実に得点源にする。この戦略が今の宅建試験では非常に有効です。9月に入るまでに全分野を1周できていれば、模試にも対応できる土台が整います。
全然進んでいない人は「これ」をやろう!
そして、もし今の時点でほとんど学習が進んでいないとしても、まだ間に合います。今から始めて合格を目指すには、迷わず宅建業法からスタートしてください。最初は問題集の解説を読みながら、どういう問題が出るのかをつかむことから始めましょう。参考書を最初から読むのは、今からでは時間的に間に合いません。問題と解説を通して、出題傾向を理解することが先決です。最初は理解できないかもしれませんが、繰り返すうちに知識がつながり、少しずつ自信が生まれてきます。7月は宅建業法と法令上の制限を、8月はその復習と権利関係の学習、そして9月には全体をまとめていく――そんなスケジュールが現実的です。
権利関係に時間をかけすぎない
どの進捗段階にあっても共通して注意したいのが、「権利関係に時間をかけすぎないこと」です。権利関係は記述内容が複雑で、慣れないうちは思ったように得点できません。宅建業法や法令上の制限のように、“覚えれば解ける”分野ではないため、他の分野以上に「慣れ」が必要になります。しかし、ここで点数が取れなかったとしても落ち込む必要はありません。誰しも通る道です。むしろ、業法と法令を満点近く取ることを目指すほうが、合格への近道です。権利関係に引きずられて業法や法令を放置してしまうのが最も危険なパターン。権利関係の学習をしているときも、業法と法令の復習を継続することが不可欠です。これこそが、合格するための最低条件とも言えます。
学習時間が十分に確保できない人におすすめしたいのが、「耳学(みみがく)」です。自分の声で問題や解説を録音し、Bluetoothイヤホンで何度も聞く。耳からのインプットは移動中や家事の合間など、すきま時間を最大限活かせる学習法で、特に遅れを取り戻したい人には非常に効果的です。問題文の言い回しに慣れることで、選択肢の判断も早くなります。試験本番では1問にかけられる時間は限られているため、1回読んだだけで正誤を判定できるようにする“感覚”を磨くには、この方法が非常に役立ちます。
今からでも大丈夫!
最後にもう一度お伝えします。宅建試験において、特に7月以降の学習は“記憶の管理”と“時間の管理”が全てです。学習内容をすべて完璧にしようとするのではなく、「得点源を確実に固める」「知識を思い出せる状態にしておく」ことが合格への最短ルートになります。勉強が進んでいない人も、いまここで覚悟を決めればまだ間に合います。あなたの行動次第で、今後の人生を大きく変えることができる。やるかやらないかは、あなた次第です。
(本原稿は、『大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法』の著者の寄稿です)