しかし、職務の議論なき会員制の日本企業においては、事業を整理するもなにも、実際には個々の職務についてよくわかっていない。よって整理解雇とて、職務単位ではなく、「役に立たないっぽい」「使えない」個人は誰か?といった玉虫色の議論で、人生の一大事が決められていきやしないでしょうか。
とはいえ、です。残念ながら今後もおそらく「新しい時代の新しい能力」の要請というのは、国や企業から労働者個人に向けてなされるはずです。もはやリスキリングをはじめとする能力開発は個人の生存戦略とされ、生死をかけた不断の努力を強いることができますから。そうこうしてリスキリングもいわばコンプレックス産業化させておけば、「金のなる木」。これはみすみす手放さないでしょう。
国や企業からの要請に
労働者はどう対処すべきか
だからせめて、個人はすかさず「仮に進めるとしてその成果はどう定義するのですか?」「評価と処遇について一気通貫で議論しましょう」と二の句を継いでいきたいと思っています。
言葉の啓蒙に奔走するのなら、日本型雇用慣習とのねじれの指摘、社会経済的な構造を踏まえた検討が急務だと、臆せず声を上げたいのです。もっと言えば、人材にまつわる流行り廃りをつくると〈誰が潤うのか?〉と問うてもいいでしょう。
盛田昭夫氏の『学歴無用論』。盛田がこれを著したのは1966年のことですが、なんとも色褪せない名著です。なにせのっけから、職務要件(盛田氏は「仕様書」にたとえている)の明示がない限り、欧米の新奇性ある概念だけを輸入しても徒労だと、約60年前に述べているのですから。
もしもこの盛田氏が、令和のいまも我々がメンバーシップ型雇用を所与のものにしたまま、とってつけた「リスキリング」について侃々諤々やっていると知ったら……。「安易な敷写しは、はなはだ危険なことだ」と檄を飛ばしてくれるかもしれません。
他方で、リスキリングのような何かしら新奇性のある概念を称揚すると、その機運を高める部隊(サービス)が有象無象に現れ、問題を個人化して危機感を煽り、見事に一大産業化する流れ――能力開発というコンプレックス産業――がここまでのものになるとは、盛田氏とはいえ想像しなかったでしょうね。
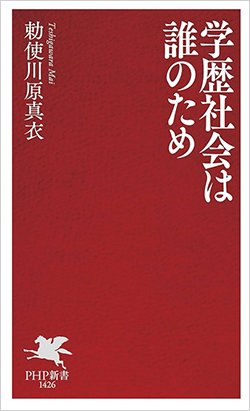 『学歴社会は誰のため』(勅使川原真衣、PHP研究所)
『学歴社会は誰のため』(勅使川原真衣、PHP研究所)







