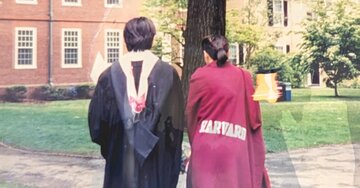2025年7月、早くも2027年3月卒業の学生の就職活動がスタートしている。近年、就職活動はますます早期化・長期化の様相を呈している。そんな中で、17年連続売上No.1を更新し続けている『絶対内定2027』シリーズは、不安な就職活動におけるお守りのような一冊だ。激変する就職活動にどう取り組んでいけばよいのか、本書の共著者であり、キャリアデザインスクール・我究館館長の杉村貴子氏に、就活生とその親が絶対に心得ておくべきポイントを聞いた。本稿では、2026年卒が直面した就職活動の変化と今後の展望、そして近年必須となりつつあるサマーインターンシップに参加することの重要性について語ってもらった。(取材・文:奥田由意、撮影:池田宏、企画:ダイヤモンド社書籍編集局)
 撮影/池田宏
撮影/池田宏
もはや「通年採用」化している
2026年卒の就職活動は、2025年卒の就職活動と比べ、さらに早期化が進んでいます。
中には大学1~2年生のうちに内々定を出す企業もあるなど、もはや「通年採用」といっても過言ではない状況となっています。従来の「早期選考」という言葉すら死語になりつつあると感じるほど、就職活動のかたちが根本的に変わってきました。
現在多くの企業で見られるのは、夏期に実施されるサマーインターンシップがそのまま選考の入り口となるパターンです。業界を問わず、「サマーインターンシップからしか採用しない」という企業も増えています。三菱地所が2027年卒のサマーインターンシップの開催を見送ることを発表して話題になっていますが、やはり多くの企業ではサマーインターンシップを実施しているのが実情です。
例えば、ある金融業界大手では、執行役員が「サマーインターンシップに“応募した人”以外は本選考では採らない」と明言しています。詳しくは後述しますが、応募した結果サマーインターンに参加できなかった場合は別として、そもそも応募すらしていない場合はその企業への志望度が低いと見なされることがあるのです。
■「選考①」と「選考②」の時代
このような状況を踏まえると、もはや「早期選考」「本選考」という従来の区分けではなく、「選考①がインターンシップ(サマーおよび秋・冬)」「選考②が本選考」と考えるのが実態に近いでしょう。
2026年卒の就職活動では、ほぼ全ての業界の大手企業が本選考前に内定を出していました。このため本選考は、学生にとっては「リベンジ」できる機会であると同時に、企業にとっては「二次選考」のような位置づけになっているとも言えます。
これには企業側の事情も関係しています。近年では、就職活動の長期化により、学生1人当たり2~3社の内定を取得することが当たり前になりました。そうなると、内定辞退される企業が学生1人当たり1~2社出てしまうわけです。採用計画が立てにくくなった企業にとって、本選考は内定辞退者の枠分を補うという意味合いも強くなっているのです。
サマーインターンで落ちても
「リベンジ」は可能
ここで重要なのは、先ほども述べたようにサマーインターンシップの選考で落ちたとしても、応募していた事実が評価されるということです。
サマーインターンシップから内定に至る枠には限りがありますが、選考を通過するかどうかよりも、「きちんと応募している」という熱意が企業に伝わり、本選考での「リベンジ」が効くのです。
実際、最終的に第一志望内定率94%となった我究館の学生も、就職活動をはじめて数ヵ月後に始まるサマーインターンシップで、希望通りの結果が出る学生は全体の3~4割程度です。
つまり、6~7割の学生は最初のチャンスを逸しているということです。しかし、そこから継続して努力し、成長し続けることで、秋冬インターンシップから本選考が本格化する直前の12月頃には、我究館の実績で言えば7~8割の学生が内定を獲得しています。
そして興味深いことに、12月までに第一志望の内定を獲得する学生も7~8割にのぼります。
ただし、多くの学生はそこで就職活動を終えるわけではありません。就職活動を進める過程で視野が広がり、「この企業も受けてみたい」「以前落ちた企業に『リベンジ』したい」という気持ちが生まれます。このため、ほとんどの学生が内定獲得後も、本選考まで就職活動を続けることになります。