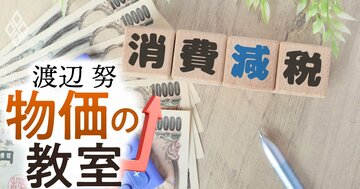なぜ物価が上がり続け生活は苦しいのか
モノやサービスの値上げが私たちの生活を苦しめるようになって久しいが、ここ数カ月間だけでも「追加値上げ」の動きが目立っている。企業はコストアップ分を価格に転嫁せざるを得ない状況だ。中でも、家計にとってインパクトが大きいのは食料品だろう。
帝国データバンクが主な食品メーカー195社を対象に行った調査によると、7月に値上げされる食品は2105品目にも達するという。また、この数カ月は「令和のコメ不足」が深刻化した。コメの一時的な値上がりによる、原材料の仕入れ価格上昇も一因にあるだろう。
一方、株式上場している食品大手の営業利益は前年度比0.9%増(25年3月期ベース)と、事実上の横ばいだ。決算会見や株主総会などでも、原材料価格の上昇が各社の収益性を圧迫しているとの話をよく聞く。
企業がモノやサービスの値上げに踏み切る場合、原材料費や人件費などのコストアップ分を価格に転嫁するのがコストプッシュ型インフレだ。一方、需要の高まりが先にあり、企業が価格を上げても需要がついてくる判断するケースは、デマンドプル型インフレと呼ぶ。
今や自動車や一般用(OTC)医薬品の価格も、コストの増加を主な要因に値上げしている。しかしコストプッシュ型のインフレは製造業にとどまらず、幅広い業種で明らかだ。代表的なのが飲食、宿泊、交通や物流などの分野で、料金引き上げを表明する事業者が増えている。
例えば、ヤマト運輸は10月から宅急便の運賃を平均で3.5%値上げする。人件費の増大が値上げの主な要因といえる。物流業ではドライバー不足が問題視されている。同じことは建設や医療、介護といった分野にも当てはまる。タクシーや路線バス、鉄道でも、初乗り運賃を引き上げることでコスト増加分の価格転嫁を急ぐ事業者が増えている。