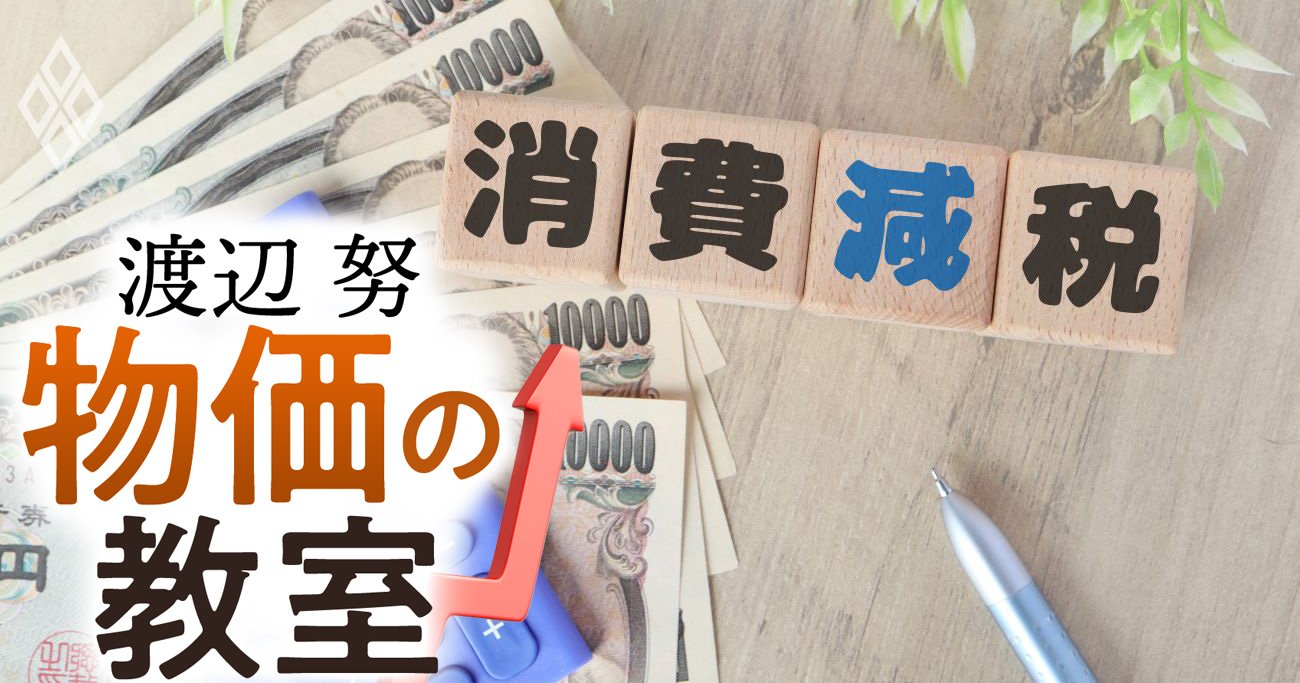 Photo:Yusuke Ide/gettyimages
Photo:Yusuke Ide/gettyimages
消費税減税が参院選の争点に浮上している。各党がこぞって税率の引き下げを打ち出す一方で、「減税すれば消費者は必ず得をするのか」という本質的な問いは置き去りにされている。価格への転嫁が不完全であれば、減税の恩恵は売り手に吸収され、消費者の懐は潤わない可能性もある。日本で実施された3度の消費増税や、欧州の減税事例から何を学べるのか。価格の転嫁率という視点から、減税の実効性に迫る。(ナウキャスト創業者・取締役、東京大学名誉教授 渡辺 努)
消費税減税を巡る論争に欠けている視点
消費税減税が、参院選の争点として浮上している。
例えば、国民民主党は「実質賃金前年比がプラスになるまで税率を5%に引き下げる」、立憲民主党は「食料品の税率を1~2年程度0%にする」、日本維新の会は「食料品の税率を27年3月まで0%にする」と提案している。消費税撤廃への支持も根強い。一方、自民党は消費税減税に消極的な姿勢を取っている。
消費税軽減で消費者の負担を減らし個人消費をテコ入れしようというのが支持派の主張だ。それに対して反対派は、消費税収は社会保障費の重要な部分を担っており、減税すると社会保障を維持できなくなると主張する。
消費税減税を巡るこれまでの議論では、後者の財政の視点が強調されてきたというのが筆者の印象だ。それとの対比では、「消費者の負担軽減」という、前者の視点が真正面から議論されることは少なかった。
その前提には、消費税は消費者から徴求される税なので、減税されれば自動的に消費者が潤うというナイーブな信念があるように思う。だが、そもそも消費税減税で消費者が潤うというのは本当だろうか。
消費者の懐を潤すかどうかは、消費税減税によって消費者が商品を買う際の価格が下がるか否かに依存する。
例えば、消費税の税率が10%から7%に下がるとする。税率低下分の3%だけ価格が下がるとすれば、消費者の経済厚生は確かに向上する。これは消費税減税が価格に100%転嫁されるケースだ。
しかし、税率が3%下がったとしても価格は1%しか下がらないこともあり得る。
税率変更のタイミングで、売り手が課税前価格を2%引き上げたとすれば、課税後の価格は1%しか下がらない。この場合、税率引き下げ分(3%)のうち3分の1は消費者に渡るが、残りの3分の2は売り手に行ってしまう。消費者の経済厚生は減税で改善するものの十分ではない。
このケースでは、消費税率の低下幅が3%に対して課税後の価格の低下は1%なので、転嫁率は0.33だ。
もっと極端な場合、転嫁率はゼロになるかもしれない。そうなると消費税減税を行っても消費者はまったく豊かにならず、潤うのは売り手だけということになってしまう。
では、仮に日本で消費税減税を行う場合、転嫁率はどの程度になるのだろうか。消費税減税で消費者は本当に豊かになるのだろうか。もし転嫁率が低く消費者に十分な恩恵が及ばないのであれば、転嫁率を引き上げる手だてはあるのだろうか。以下ではデータを用いてこれらの点を検討する。







