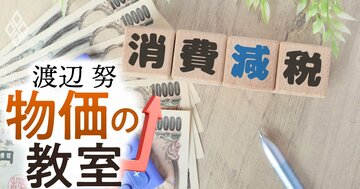物価上昇の要因は円安から人件費へシフト
企業のコスト増加要因が変化しているのは先に述べた通りだ。21年から23年までは円安と、エネルギーや食料価格の世界的な上昇が主な要因だった。それが今、人件費の増加にシフトしている。詳しく、企業物価と企業サービス価格の推移から確認してみよう。
日本銀行によると、6月の企業物価指数は前年同月比2.9%上昇した。5月は同3.2%上昇だった。わが国の企業のコストは、依然として上昇基調にある。
コスト増加の主要なファクターでは、以前に物価上昇をもたらしていた輸入物価の影響は小さくなっている。1月以降、円ベースで見ても、契約通貨ベース(円換算せずに全ての調査価格を契約通貨のままで集計)で見ても、輸入物価は前年同月の実績を下回っている。トランプ関税の発動や米財政への懸念が上昇したことによって、1~6月、円はドルに対して8.5%上昇した。資源の価格も不安定で下落した。
一方、企業向けサービス価格指数は上昇傾向にある。22年、23年、24年それぞれ年平均の上昇率は1.5%、2.2%、2.9%だ。そして5月は前年同月比3.3%上昇した。業種別に見ると、宿泊、機械の修理、ソフトウエア開発、物流と、人手不足が深刻な分野で価格上昇が明らかだ。このデータからも、人件費の増加が物価の上昇の主な要因であることが確認できる。
人件費増加は、春闘の結果からも確認できる。25年の賃上げ率は平均5.25%に上昇した。1991年の5.66%以来、34年ぶりの高水準だ。また、新卒者の初任給を30万円台に引き上げる企業も増えている。賃金を引き上げることが難しいと、他社に優秀な人材を引き抜かれ、最悪の場合は事業運営に行き詰まることも懸念される。
人件費の増加により、経済全体で見た企業の粗利率は低下傾向にあることが考えられる。消費者物価を企業の販売価格として、企業物価を売上原価として差を計算すると、ここ1年程度の間、両者の差はゼロ近傍で推移している。付加価値創出の効率性は低下している。