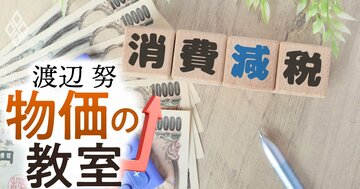写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
7月20日に参議院選挙が迫る中、日本経済の本当の課題を突き詰めて考えたい。「バラまき」とも批判される政府の給付金や賛否両論ある減税などではなく、日本経済を根本から良くするための課題解決が求められるはずだが、それは何か。(多摩大学特別招聘教授 真壁昭夫)
当面、私たちの生活は楽にならない
総務省によると5月の消費者物価指数は2020年の平均を100として111.4となり、前年同月に比べて3.5%上昇した。数年前まではデフレに苦しんできたわが国が、主要先進国の中で今、最も高いインフレ率になっている。欧米諸国の多くでは、いったん物価上昇が沈静化しつつある中、わが国は周回遅れでインフレに苦しんでいる。
わが国の物価上昇は、主に企業のコストアップ分を価格に転嫁する動きによるものだ。つまり、コストから圧迫される「コストプッシュ型」のインフレだ。それは、需要が高まって価格が上昇する、「デマンドプル型」インフレとは異なる。ある意味では、あまり好ましくない物価上昇といえる。
21年から23年ごろの物価上昇は主に円安と、世界的なエネルギーや食料などの価格上昇を掛け算した影響が大きかった。しかし、ここにきてコストアップ要因は、人手不足による人件費の上昇に変わりつつある。
製造業と非製造業の両方で、人手不足はかなり深刻になっている。企業は人員確保のために賃金を上げざるを得ない。逆に言えばようやく、わが国の給与も上がる土台ができた。日本の人口減少は構造的な問題で解決の糸口は見つかっていない。今後も人件費は増加傾向になるだろう。
問題は、給与の上昇と物価上昇のペースがうまくバランスするかだ。足元、食料品をはじめ生活に欠かせないモノやサービスの価格上昇率は、名目賃金の上昇ペースを上回っている。ということは当面、私たちの生活は楽にならないだろう。
この状況を打破するには、政府の給付金ではなく、日本経済を根本から良くするための課題解決が求められるはずだが、それは何か。