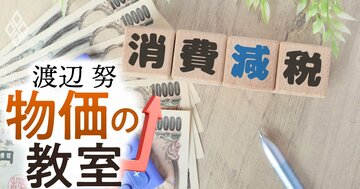格差拡大は国力の低下につながる
わが国の24年の合計特殊出生率は1.15に低下した。統計開始以来で初めて年間の出生数が70万人を下回った。少子化、高齢化、人口減少の加速は避けられない。6月の日銀短観では、調査対象企業の全分野の企業が、「人手不足は深刻化する」と回答している。
企業はこれまで以上に賃上げを実行し、採用を増やし人手をつなぎ留める必要がある。そのため今後も、人件費増加によるコストプッシュの圧力は高まると予想される。その流れから、商品の追加値上げを実行する企業は増えるはずだ。ということは当面、物価の上昇はなかなか止まらない。
日銀短観では、大手製造業の中でも、特に素材系企業の値上げ意欲が強いことが分かる。企業間で値上げ交渉は激化し、企業物価に追加的な押し上げ圧力はかかりやすくなっている。企業が成長を目指して、価格を引き上げること自体は必要なことだ。
ただ、経済全体で見ると、中小企業の価格交渉力は大企業を下回る。この点は、わが国全体で見た、実質賃金が安定的に伸びない一因だろう。当面、名目賃金の緩やかな上昇ペースが、物価上昇に追い付かない状況が続く可能性は高い。
今後、賃上げの余裕がある大企業の従業員、あるいは金融・実物資産を持つ資産家と、そうではない人々の経済格差は拡大するだろう。実際、物価上昇により、生活を見直して支出を切り詰めなければならない人が増えていると聞く。また、子育て世帯は教育費が大きな負担となっており、見直しに迫られる世帯もあるなど、社会問題化しつつある。
こうした状況は個々の家計の問題にとどまらず、国力の低下につながる問題だ。わが国の経済課題は、目先の減税や給付ではなく、中長期的な視点に立った経済力の強化に尽きる。しかし、7月20日に迫った参議院選挙における議論を見る限り、そうした主張があまり見当たらないのは大変残念だ。
繰り返しになるが、このままだと人件費の増大によりコストプッシュ型の物価上昇圧力は高まるだろう。実質賃金は伸び悩み、個人消費の減少をはじめ内需の縮小均衡も加速する「負の連鎖」のリスクを今一度、考えたい。