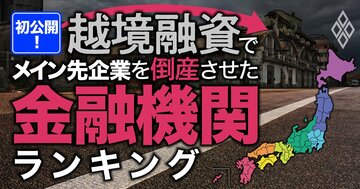先の第1回トポス会議が開催された頃は、AI研究の世界的権威であるレイ・カーツワイル氏が提唱した、コンピュータが人間の知性を凌駕するという「シンギュラリティ」が話題になっており、もっぱらコンピュータvs.人間という対立関係の下、議論されていた。
しかし、こうしたコンピュータ優位を前提とし、矛盾や対立、あいまいさなどの定性的なものを排除し、優劣や主従という二元論、何事も数字で説明しようとする論理合理的なアプローチに偏っては、創造性やイノベーションの芽は摘まれてしまう。そこで、知識創造という視点から、二項動態というアイデアを提示して、第1回トポス会議を締めくくった。
ちなみに、その翌2013年には、オックスフォード大学のマイケル・オズボーン氏が「AIが実装されれば、47%の雇用が失われる」という衝撃的な論文を発表し、しばらく人々の関心をさらった。しかし、世の中における仕事は一定量しかなく、それゆえAIとの奪い合い、早晩奪われてしまうという予測は、経済学の「労働塊の誤謬」の通り、ほどなく見向きされなくなった。
ただし、AIに限らないが、偏りや過信は危ういし、害をもたらしかねない。たとえば、欧米企業の不正会計に端を発したガバナンス改革が日本にも飛び火して、法令遵守義務(コンプライアンス)やコーポレートガバナンス・コードの遵守などが新しいルールになった。しかし、リスクや失敗を恐れる気持ちが生み出したオーバーアナリシス、オーバーコンプライアンス、オーバープランニングといった過剰な反応が派生し、組織とそこに働く人たちの創造性や野性を劣化させ、機動力やリスクを取るチャレンジ精神まで弱体化してしまった。もちろん、「昔はよかった」と懐かしんでいても現状は変わらない。考えるべきは、こうした縮み志向からいかに脱却するかであろう。
そのためには、「人間とは、未来の共通善に向かって他者とともに新たな意味や価値を創造する動的な主体である」という人間観に立ち戻ることが有効ではないか。われわれは、このような人間観の下、組織的知識創造理論を発展させてきた。
イノベーションや新規事業開発において、こうすれば実現するという成功方程式はない。確率を上げる方法はいろいろ提唱されてきた。「経営の神様」といわれた松下幸之助翁は「最高の経営は衆知による経営である」と述べたように、その有力な一策が衆知による全員経営である。最近は「集合的知性(collective intelligence)」という言葉もあるが、暗黙知も含めた一人ひとりの潜在能力を解放し、結集する「集合知(collective knowledge, collective wisdom)創造」が重要である。
また、ただ足し算で集めればよいというものではなく、ウィリアム・ロス・アシュビーが「複雑な環境に対応できるシステムとは、それと同じだけ複雑なシステムである」と述べたように、事業環境の多様性にはこれに対応できる多様性を担保する必要がある。
まさに形式知レベルでは集合知の塊であるAIと、そこに集う人間の暗黙知を含めて多様性豊かな場が一体になることで、暗黙知と形式知の相互変換運動が活発になり、イノベーションや新規事業のシーズが創発してくる可能性が高まる。AIは、こうした知識創造の好循環モデルを実現する大きな手段となる。つまり、SECI(セキ)プロセスで説明している、個人の暗黙知を概念など集団の形式知へと転換するフェーズ(表出化)、あらゆる形式知を自在に組み合わせて組織知へと変換するフェーズ(連結化)、そして組織知を実践を通じて身体化し、個人の暗黙知を豊かにするフェーズ(内面化)を強化・活発化するのではないだろうか。
ただし、あくまで組織的知識創造の起点は、他者や環境すべての暗黙知を共有するフェーズ(共同化)である。マイケル・ポランニーが「すべての知は暗黙知に根差す」と述べたように、動く現実のただ中で、直接経験を通じて「いま・ここ」の暗黙知を創発することから、組織的知識創造のスパイラルは駆動し始めるからだ。
つい最近、これをまさしく証明する例が飛び込んできた。応氏(おうし)杯をご存じだろうか。囲碁の世界一を決める棋戦で、1988年に始まり、囲碁のオリンピックと呼ばれる。その二つ名が示すように、4年に一度オリンピック開催年に開かれる。優勝賞金は、40万米ドル(およそ6000万円)だという。第1回から優勝は中国と韓国のどちらかで、日本を含めた他の参加国は大きく水を開けられていた。しかし2024年の第10回大会では、ついに日本人が優勝に輝いたのである。一力遼(いちりきりょう)氏だ。
この栄誉は、もちろん一力氏の個人的な努力の賜物とはいえ、彼は日本の囲碁界の底上げを図る改革を試みた。ビジネスの言葉でいえば組織変革である。一力氏は、日本の棋士が世界戦で勝つためのさまざまな体制づくりが不可欠と考え、日本棋院にそのことを進言した。そして、年齢や性別を超えた勉強会、ベテラン棋士と若手棋士の対戦など、SECIモデルでいうところの「共体験」の場づくりに努めた。
将棋の世界と同じく、若手棋士たちはすでにAIを利用したトレーニングを積極的に取り入れており、時にはベテラン棋士を打ち負かすこともあり、ベテラン棋士たちも若手に倣ってAIを活用するようになった。言い換えれば、AIという集合的知性を収集・蓄積する装置を最大限活用し、武装した個人同士が切磋琢磨し合う共体験の場が生まれたのである。しかも、一力氏はAIが考えもつかなかった打ち手を編み出したそうだ。人間がAIを超えた瞬間であったからといって、人間がAIに勝ったとか、そういう優劣ではなく、やはり二項動態なのだ。
AIが人間の秘められた可能性を引き出し、その結果さらに賢くなった人間がAIを進歩させる。経営とは「生き方(a way of life)」である。「何のために生きるか」「何のために存在するか」という共通善に向かう存在目的を問うことが、二項動態を意味づける。こうした共進化を望む。
2024年12月
一橋大学 名誉教授 野中郁次郎