多くの国では、「金銭解雇」のルールがある。OECDの国の中でルールがないのは、日本と韓国だけだといわれている。日本でも大企業のように強い労働組合がある会社では、解雇の場合には相応の補償を得ることができる。しかし、多くの中小企業では、解雇された労働者は泣き寝入りするしかない。
現状では、労働市場は変化の方向にある。しかしそれでもあえて極論すれば、日本の労働者の選択肢は2つしかない。金銭的な補償もなく、身一つで泣き寝入りして辞めていくか、何があっても我慢して会社にしがみついて残るかである。
極めて不合理なことである。終身雇用・年功序列こそが唯一の正しい働き方であるという考え方は、労働者を会社に閉じ込めていることにほかならない。そのような不公平なことがあってよいはずはない。だからルールをつくる必要がある。しかし、日本ではなぜか「金銭解雇」という言葉に、極端なアレルギーがある。
数字が示す明らかな誤解
「派遣労働で格差が拡大」
もう1つの例を紹介しよう。
『ハケンの品格』というテレビドラマが人気を博したのは2007(平成19)年ごろだった。「派遣」は「自由な働き方」を実現する1つの方法である。しかし、「小泉内閣のときに派遣労働者を増やして、所得格差が拡大した」と言われた。これは、誤解に基づいた暴論としかいいようがない。
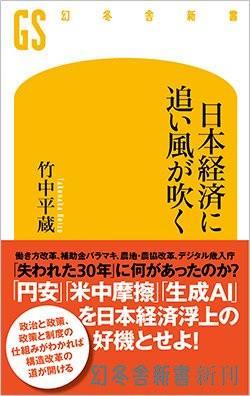 『日本経済に追い風が吹く』(竹中平蔵、幻冬舎新書)
『日本経済に追い風が吹く』(竹中平蔵、幻冬舎新書)
まず、小泉内閣で派遣を増やしたわけではない。1997(平成9)年6月に、ILO(国際労働機関)は「民間職業仲介事業所に関する条約」を採択した。働きがいのある人間らしい仕事(「ディーセント・ワーク」)を実現するために、民間職業仲介事業所の果たす重要な役割を認識し、それを利用する労働者の保護を図ることを目的とした条約である。日本は1999(平成11)年7月に批准した。森喜朗内閣のときである。批准の5年後の2004(平成16)年に製造業について実施した。
次に、「派遣労働者」について。2003(平成15)年には正社員が65.4%、非正社員が34.6%だった。非正社員の内訳を見ると、パートタイム労働者が23.0%で最も多く、契約社員が2.3%、派遣労働者は2.0%に過ぎない。その後、2017(平成29)年には3.2%、2022(令和4)年には4.0%になっている。
全労働者に占める派遣労働者の割合は依然として非常に低い。さらに、「格差は拡大」しているわけではない。所得格差の度合いを測る指標として使われる「ジニ係数」は、1990年代から2000年代にかけてほぼフラットに推移しているからである。







