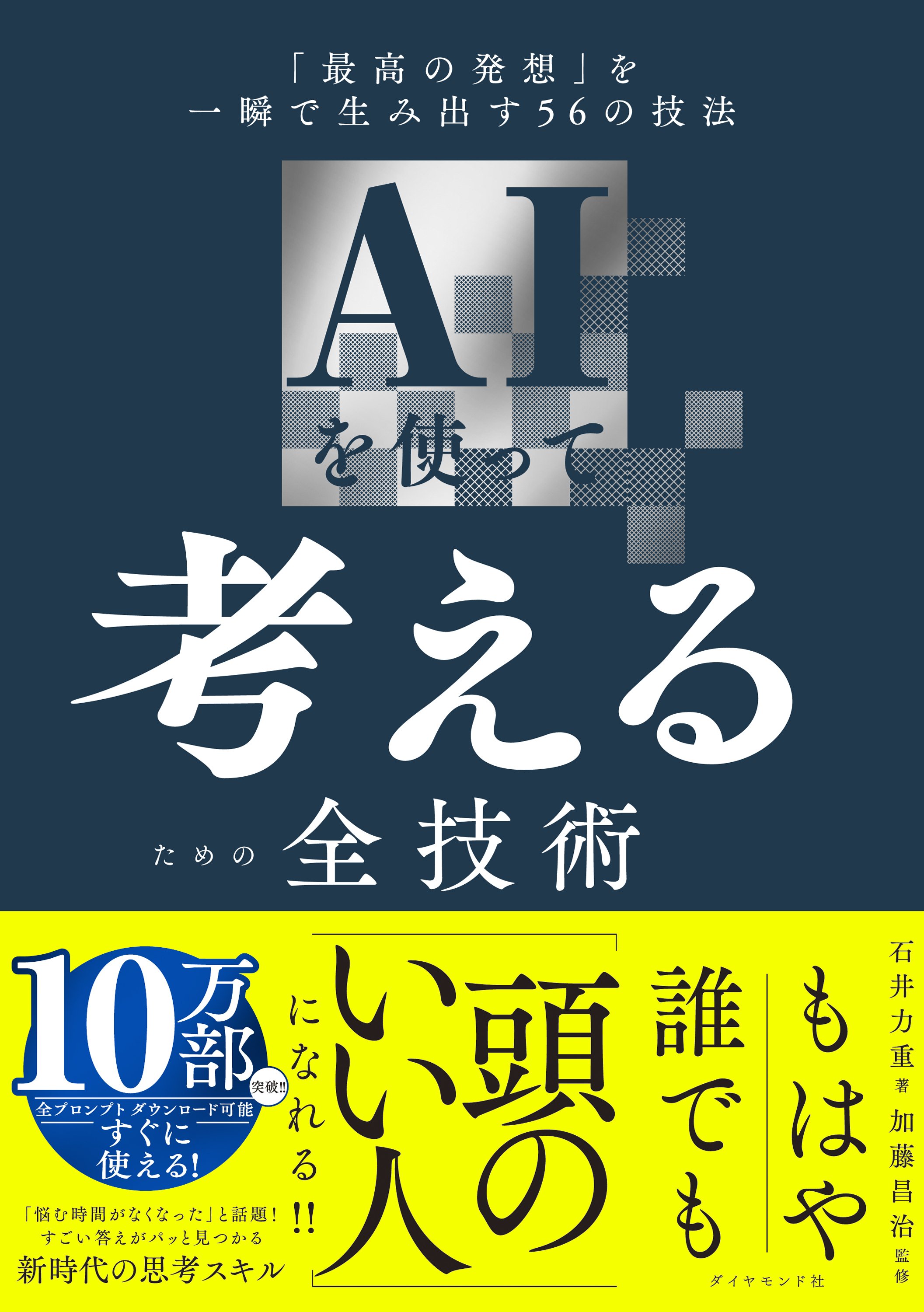AIをうまく使えば、人生から「悩む時間」を消すことができます。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「めちゃくちゃ充実している!」「値段の100倍の価値はある」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「未来から逆算する」という考え方
「バックキャスティング」という考え方があります。ワード自体にはある程度聞き馴染みがあるのではないでしょうか。
まず10年後や20年後と、はるか未来を予想します。そして「10年後が~~なら、その6~7年前だとまだ~~の段階だろうから、今から3年後は~~な感じかな?」と考える発想法です。途中経過は考えずに、着地点から逆算して考えます。いったんはるか遠くまでロケットを飛ばして、着地したロケットの中から旗の立ったラジコンカーがパカリと出てきて、到着地点から現在地まで戻ってくるイメージです。
「現在を基準にしてアイデアを考えてみたけれど、どうもパッとしない予定調和的になりそう……」
「業界予測データをもとに考えても、競合企業と同じアイデアしか出ない気がする……」
そう悩んでいるとき、あるいは、商品・サービスや事業の将来像が想像しにくいときに、バックキャスティングの発想法が役立ちます。
過去の変化を踏まえた現実的な未来を予測する方法
一方で「いきなり10年後なんて、見当もつかない」「アイデアが突飛になりすぎてしまうのは困る」「もう少し、現実的な未来予測をしたい」という人もいるかもしれません。
そんな方におすすめしたい発想法があります。
それは「先見倍歴」と称する発想法。
いきなり未来を考えるのではなく、過去数年分の変化を振り返り、それを踏まえて未来予想をする発想法です。「いったん過去へ戻る→思考の助走をつけて→未来へエイッと跳躍する」というプロセスでアイデアを出します。
「先見倍歴」というネーミングは私のオリジナルですが、ベースになっているのは、「9ウインドウズ」という手法。それをよりシンプルに実践できるよう改良したのが「先見倍歴」です。
未来を想定してから、現実に戻りつつアイデアを考えていく。このプロセスはバックキャスティング発想法と共通しますが、一度過去を振り返ることで、遠い未来予測の精度が高まります。
バックキャスティング発想法のように、大きくジャンプして未来を想定することが苦手、不慣れだという方にもおすすめです。そしてなにより、過去の変化分から推定するがゆえに説得力のある回答になるため、「なぜそのアイデアなのか?」などと問われやすい社風が堅めの組織でも使いやすいのです。
AIで過去の振り返りと未来予測をする技法「先見倍歴」
さてこの「先見倍歴」、過去を振り返って未来予測をするとはいえ、誰もが簡単にできるかと言うとそうではないでしょう。
過去を振り返るだけでさえ多くの時間と手間がかかりますし、その上、過去と同じ分だけ未来が変化すると考えてはいけません。なぜならイノベーションは加速するから。過去10年分に起こったのと同じ変化が、これから3年や5年の間に訪れても、まったくおかしくないのです。その変化の加速度を踏まえて、未来を見通す必要があります。
そんな複雑な工程も、AIを使えば数分で結果までたどり着けます。
それが技法その16「先見倍歴」です。
AIに以下の段取りを指示することで、アイデアを出してもらいます。
・第1ステップ
対象(=製品や事業)を取り巻く現時点の「社会環境」と「技術要素」について列挙してもらう
社会環境とは、つまり「外の視点」。まずは対象を取り巻くもの、つながるもの、ユーザーのライフスタイル、機能を発揮するための社会インフラなどを整理します。そして技術要素とは「内の視点」。対象のなかに含まれている要素、使われている部品、材料、テクノロジーなどを整理します。外部環境と内部要素の2種類を分けて把握するのが第1ステップです。
・第2ステップ
「環境要素」と「技術要素」における、過去の変化を洗い出してもらう
次に、過去の変化を調べ、対象である製品や事業にすでに起こったイノベーションを把握します。ここでは実際に予測したい「数年先」の「2倍分」の過去を振り返ります。繰り返しになりますが、変化の速度は加速するからです。プロンプトでは一般論的に予想したい未来を「15年(=N)先」としています。そのため「過去30年(=N×2)分」のイノベーションを調査します。これが第2ステップです。なお実践する際は、Nの値を状況に応じて書き換えてかまいません。
・第3ステップ
過去に起こったのと同じだけの変化・イノベーションが、現在から未来までも続いていくと仮定するとどうなるかを推定してもらう
一度、過去と同じだけのイノベーションが今後も起こるだろうと推定します。これも、この発想法の特徴です。これが第3ステップ。
・第4ステップ
未来に起こると想定した「社会環境」「技術環境」の変化が、その半分の期間で実現されると仮定し、その仮定に基づいて「製品」「事業」の姿を構想してもらう
そして最後に、その変化が「2倍の速度で訪れたら?」と仮定して、変化の加速度を踏まえた未来予想を出します。
この第1から第4までのステップを工学的に処理することで、イノベーティブなアイデアを求めます。
それを一発で実行できるのが、このプロンプトです。
「先見倍歴」という未来予測の方法を定義します。
❶対象(「製品」または「事業」)を取り巻く現時点の「社会環境」と「技術要素」について列挙します。
❷それら(「環境要素」と「技術要素」)の過去30年の変化を洗い出します。
❸その変化分と同じだけ、現在の時点から発展させたら、それら(社会環境や技術要素)はどのぐらい変わるか、を推定します。
❹過去30年の変化分は、未来の15年間の変化分に相当すると仮定します。未来(15年後)に対象を取り巻く「社会環境」や「技術環境」をもとに、未来の対象(「製品」または「事業」)の姿を構想します。
この「先見倍歴」を用いて〈アイデアを得たい対象を記入〉の15年後の姿を予測してください。
※「15年後」を予測する場合を書いています。状況に応じて書き換えてください
文章で説明するとかなり長くなってしまうのですが、このプロンプトを使えばすべてAIが処理してくれますので、簡単にアイデアまでたどり着けますからご安心を。
技法その16「先見倍歴」、ぜひ活用してみてください。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、分析、発想、発展、具体化、検証、予測といった“頭を使う作業”にAIを活用する方法を多数紹介しています)