このスタディから発信された東京大学高齢社会総合研究機構の田中友規先生らの研究によると(注4)、オーラルフレイルを表す6項目(後述)の指標のうち3項目を満たす人は、2項目以下の人に比べて生存曲線に有意な差があるとしており、4年経過後にはフレイルや要介護に陥るリスク、死亡するリスクが2倍以上高いという報告がなされました。
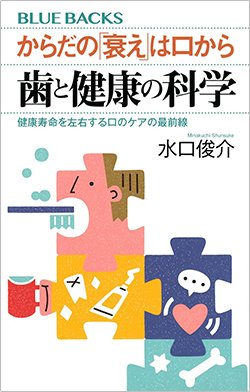 『からだの「衰え」は口から 歯と健康の科学 健康寿命を左右する口のケアの最前線』(水口俊介、講談社)
『からだの「衰え」は口から 歯と健康の科学 健康寿命を左右する口のケアの最前線』(水口俊介、講談社)
ここでいう6項目とは、(1)残存歯が20本未満、(2)咀嚼能力の低下(色変わりチューインガムでの評価)、(3)滑舌低下(舌や唇の運動の巧緻性を調べるオーラルディアドコキネシスという方法で、「タ」の発音の回数をカウントする)、(4)舌圧の低下、(5)かたいものが食べにくくなったか、(6)お茶や汁物でむせるか、です。
この6項目のうち3項目が合致した場合、4年後の要介護や死亡のリスクが2倍以上だったというのは、大変衝撃的です。
もちろん、この研究だけでなく、「オーラルフレイルを防ぐために介入した結果、リスクが減少した」という研究がなければ、オーラルフレイルを防ぐことの重要性が完全に証明されたわけではないことも付け加えておきます。
このように、「口腔機能の回復維持が、要介護を遅らせて健康寿命の延伸に貢献する」という可能性が広く知られつつあります。
(注4)Tanaka, T., Takahashi, K., Hirano, H., et al. Oral Frailty as a Risk Factor for Physical Frailty and Mortality in Community-Dwelling Elderly. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 73, 1661-1667, doi:10.1093/
gerona/glx225 (2018).
gerona/glx225 (2018).







