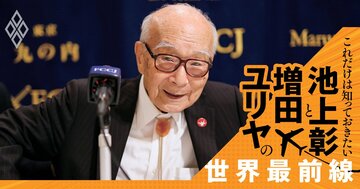しかし、では公平に、ということにすると、「すべての国が核兵器を持たないか、すべての国が核兵器を持つか」のどちらかになります。そして核兵器廃絶が現状では難しいということを考えると、公平さを重視することは、核兵器の拡散を招いてしまいかねません。
つまり、すべての国が公平に核兵器を持つ「恐怖の拡散」よりも、不公平だが核保有国の数を限る「恐怖の独占」のほうがマシ、というのが現在の核不拡散体制の基本的な考え方になっています。国連でP5(編集部注/permanent members5すなわち、国際連合安全保障理事会の常任理事国であるアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国の5ヵ国のこと)の拒否権を認めているのと同じように、主権国家システムのなかで、あえて不公平さを受け入れているのです。
しかしそもそも核不拡散条約に入っていないインドやパキスタンが核兵器を保有するようになりましたし、北朝鮮やイランによる核開発もおこなわれていることで、核不拡散条約が想定したような「恐怖の独占」が崩れ、「恐怖の拡散」が生じつつあります。
イスラエルが核兵器を保有していることも、公然の秘密とされています。
私は核兵器を捨てるから
あなたも捨ててください
核不拡散とともに、核兵器の数を増やさないとする核軍備管理や、核兵器の数を減らす核軍縮への取り組みも進められてきました。
核軍備管理としては、1963年に署名された部分的核実験禁止条約(ただし地下での核実験は可能)や、1972年に署名された戦略兵器制限条約(SALT)があります。
また1987年に中距離核戦力(INF)削減条約が、冷戦終結後の1991年には戦略兵器削減条約(START)が署名され、核軍縮がおこなわれてきました。
しかし、これらの取り組みには限界もあります。1996年、国連は部分的核実験禁止条約を強化した包括的核実験禁止条約を採用するとしましたが、参加国が少なく、いまだに条約としての効力を持っていません。アメリカとソ連(ロシア)の対立によってSALTもINF条約もなくなりましたし、STARTも期限つきです。