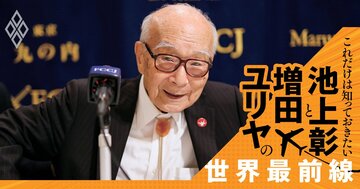それだけではなく、核軍縮そのものも一筋縄ではいきません。というのも、アメリカとロシアのあいだで核軍縮が進むことは、実は世界全体の核軍縮にとってむしろ逆効果になるおそれがあるからです。こちらについても説明しておきましょう。
アメリカとロシアが減らすなら
中国は増やす一択となる
現在、アメリカとロシアはそれぞれ5000発くらいの核弾頭を保有しています。そしてこの両国のあいだでは、冷戦時代以来の相互確証破壊が成り立っているといえます。
これに対し、三番手の中国が保有する核弾頭の数は600発くらいだといわれていますので、アメリカとロシアに大きく水を開けられています。
ところが、仮にアメリカとロシアが3000発くらいまで核弾頭の数を減らすとしたらどうなるでしょうか。中国も足並みをそろえて核軍縮に参加してくれるでしょうか。
残念ながらそうはならないでしょう。
なぜなら中国からすれば、逆にここで一気に核軍拡をおこなって、アメリカやロシアと核弾頭数の差をつめれば、これらツー・トップとのあいだで相互確証破壊の関係を築けるかもしれないからです。
つまり、二大核大国のあいだの核軍縮は、三番手に核軍拡のインセンティブを与えてしまうおそれがあります。
もし中国のもくろみ通りに、相互確証破壊がアメリカとロシアに中国も加えた3ヵ国のあいだで成立することになればどうなるでしょうか。
ここで、第一次世界大戦直前のヨーロッパの状況を思い出してください。
フランスとロシアに挟まれたドイツは、フランスとロシアの連合軍が示し合わせてドイツに攻めて込んでくるという最悪の事態を想定した備えをおこない、今度はそれに対してフランスとロシアそれぞれが最悪の事態を想定することになったため、これら3ヵ国はお互いに軍拡競争をとめられない「安全保障のジレンマ」に陥ってしまいましたね。
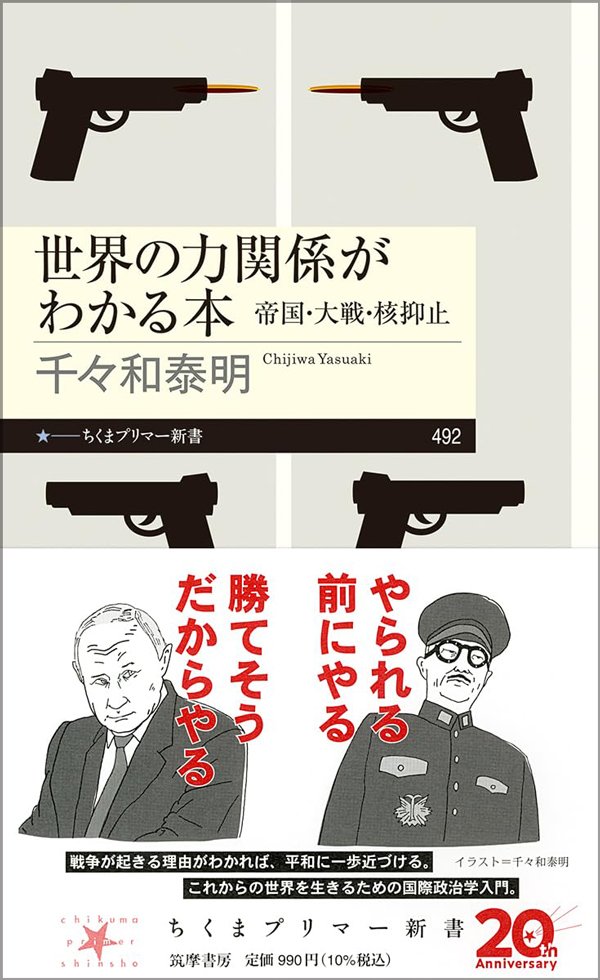 『世界の力関係がわかる本――帝国・大戦・核抑止』(千々和泰明 筑摩書房)
『世界の力関係がわかる本――帝国・大戦・核抑止』(千々和泰明 筑摩書房)
ここでこのことを当てはめると、たとえばアメリカは他の2ヵ国、この場合ロシアと中国が手を組むことを想定して、核弾頭の数をそろえなければならなくなります。ロシアも中国も同じです。
つまり、敵対国と相互確証破壊の関係を築くことができる国が2ヵ国から3ヵ国に増えると、「「核」の安全保障のジレンマ」が発生するおそれが出てきてしまうのです。
アメリカ・ロシア・中国のあいだの核軍拡のスパイラルです。核軍縮が逆効果になるというのは、このような意味なのです。