しかし、ここで気づくべきは、もし「価値」の有無で自分を愛したり愛さなかったりする親だったのだとすれば、それは条件を課してこちらを値踏みしているということであり、それは親の「欲望」であって、こちらが求めている無条件の「愛」ではないということです。つまり、もし自分が分かりやすく何らかの「価値」を生み出せたとして、それで親が突然こちらを称賛したり優しくしてきたとしても、それは生み出した「価値」に対しての反応を得たに過ぎないので、自分が欲しかったものとは質的に違うものだということに気づかされることになるでしょう。
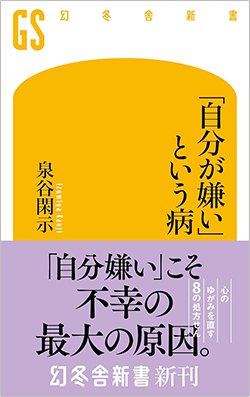 『「自分が嫌い」という病』(泉谷閑示、幻冬舎新書)
『「自分が嫌い」という病』(泉谷閑示、幻冬舎新書)
つまり、こちらが「価値」を生み出すか否かで基本的な態度を変えてくるような親は、自分を「愛して」くれているのではなく、親の分身であるかのようにこちらを捉えて「欲望」を向けてきているに過ぎないことに気づかなければなりません。
「常に価値を生み出さなければ」という思い込みは、ほとんどの場合、親との関係の中で原型が作り出されてしまうものですが、その後もずっと、自分の中で強迫観念のように付きまとってきます。仕事をすれば自分が「価値ある人材」だろうかと気になり、プライベートな関係でも自分は果たして「愛してもらえる価値」があるだろうかという不安をいつも抱えてしまうのです。
しかし、「愛」とは、決して生み出せた「価値」に向けられるものではなく、存在そのものに向けられるものです。つまり、「こうしたら愛されるのではないか」という考え方は、もうすでに条件を課してしまっているので、初めから「愛」とは逆方向の「欲望」を目指したものになってしまっています。ですから、「愛されたい」がために「価値」を生み出し続けるという努力奮闘は、どこまでいっても人の「欲望」を引きつけることはあっても決して真に求めている「愛」は得られないという、報われない構造になっているのです。







