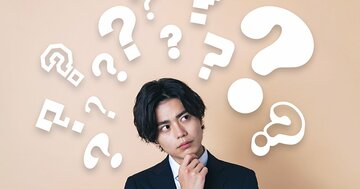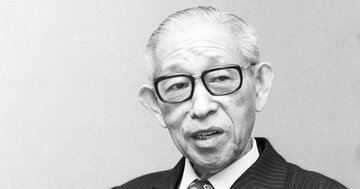写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
カリスマ的なリーダーが一人いるだけでメンバーの士気が上がる――高度経済成長期における企業文化では、熱血・根性系のリーダーがもてはやされていた。だが、令和のビジネス環境では、こうした風潮は時代遅れだ。実は、リーダーに必要なのはカリスマ性ではない。むしろ、それを凌ぐテクニックはほかにあった。
「熱血応援」ではもう動かない
かつての体育会系の部活や高度経済成長期の企業文化では、熱血系のリーダーが重宝される風潮があった。ただ一人熱いカリスマリーダーがいるだけで、メンバー全員が「うぉー!」と奮い立つような組織がざらにあった。しかし、いまのビジネス環境では、部下の多くがそんな“根性論”に冷めた目を向ける。
だからといって、組織の冷め切った空気を放置してしまうと、成果を上げる活力もエンゲージメントもないチームになってしまうのが悩ましいところだ。私自身、部下に熱い言葉をかけたり、鼓舞したりすることが得意なほうではない。
幸い現代においては、「熱血応援」の価値は薄れてきている。「どうした暗い顔して。もっと気合い入れろ!」と発破をかけるような“根性論”で乗り切れるほど、あらゆるリソースに余裕がないのだ。
メンバー自身が納得し、自発的に「走りたい!」と思える仕組みを整備しなければ組織が持たない。そこで有効なアプローチが「共感」と「共鳴」だ。
「共感」と「共鳴」は、似ている言葉だが意味が違う。部下との信頼関係構築のためには、両者の使い分けが重要である。
・共感
相手の感情を理解し、受け止めること。たとえば、部下が「今期のノルマはきつすぎる」と弱音を吐いたときに、「たしかに、今期は高めだよね」と認めてあげること。
・共鳴
相手が抱える感情や経験と、自分が抱える感情や経験が同じ波長で振動すること。「自分もまったく同じ葛藤を感じたことがある」「自分もまったく同じ失敗をしたことがある」という状態。
リーダーが部下と「共鳴」できるケースは多くない。年齢やキャリアに差があるので、まったく同じ体験をしているほうが珍しい。だからこそ、「共感」が大切になる。「まったく同じ体験ではないけれど、相手の気持ちを理解しよう」という姿勢だ。
もちろん、もし偶然「共鳴」できるなら、それはさらに強い信頼感を生む。
たとえば、部下の「顧客に意思決定を迫るのが苦手で、うまくクロージングができない」という悩みを、リーダーも新人時代に抱えており、それを克服した経験があるのなら、「自分も当時はそう感じていた」「このトークスクリプトを試してみたら?」と「共鳴」するのだ。