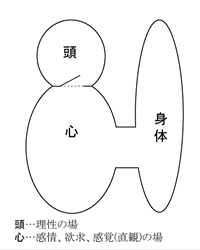泉谷閑示
毒親よりも有害な「愛と善意のポンコツ親」に育てられる悲劇【心理学者の納得解説】
暴言や暴力などで子どもの心身を支配しようとする「毒親」ばかりがフォーカスされがちだが、じつはもっと恐ろしいタイプの親がいる。心理学者の筆者によれば、子どもを愛してやまない親が「あなたのためなのよ」と振りかざすアクションには、親自身も気づかない猛毒が含まれている場合があるというのだ。※本稿は、泉谷閑示『「自分が嫌い」という病』(幻冬舎新書)の一部を抜粋・編集したものです。

「僕なんてまだまだです…」自己否定の強い若手との付き合い方とは?【心理学者が分析】
褒めてやっても喜んでいる様子がなく、いつも満たされない風でいる...そんな若手に戸惑ったことはないだろうか。心理学者である筆者によれば、彼らの背景には、「頑張らないと愛されない」という根深い思い込みがある。親の強い期待の中で育ち、自己否定と低い自尊心を抱えているのだ。愛され、認められるために価値を生み出すことに、もう疲れているのかもしれない。※本稿は、泉谷閑示『「自分が嫌い」という病』(幻冬舎新書)の一部を抜粋・編集したものです。

「それで君はどうしたいの…」自己主張のない若手が“第三の反抗期”を経験しないと一人前になれない理由
最近の若手に対し、自己主張が薄いと感じたことはないだろうか。その背景には、幼少期に反抗期を経験せず、感情や欲求を抑えて育ったという事情があるらしい。精神科医の筆者によれば、自分の意思が見えにくくなっている彼らには、いま“第三の反抗期”が必要だという。中間管理職は若者の内なる声に寄り添うことで、より円滑な関係構築ができるはずだ。※本稿は、泉谷閑示『「自分が嫌い」という病』(幻冬舎新書)の一部を抜粋・編集したものです。

第12回
――あんな非人間的な満員電車に、どうしてみんなは平気で乗っていられるんでしょう? 満員電車のギュウギュウ詰めは、パーソナルスペースを侵害されています。でもみなさんさほど苦に感じている様子がありません。感性の鈍磨していない人が吐き気を伴う不快感に襲われても不思議はないでしょう。私たちは、苦に思わないことを「正常」と呼ぶべきなのでしょうか。
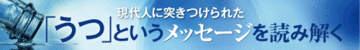
第11回
朝起きられず遅刻してしまう。復職してもまた出社できなくなる。このような症状は「自己コントロール」ができていないと捉えられがちだ。だが、人間とはそもそも「自己コントロール」しなければならないのか。
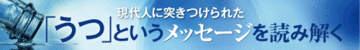
第10回
自分という「主体」が持てない人々の問題については、これまでも取り上げてきました。しかし、「主体」を持っているがゆえに理不尽な扱いを受けてしまう人々もいます。また、そのことが原因で、本人も「自分がおかしいのではないか」と疑いはじめ、その結果、「うつ」状態にまで追いこまれてしまうケースも稀ではありません。今回は私たちの属する組織や集団の体質や、それが私たちの生き辛さとどう関係しているか考えたいと思います。
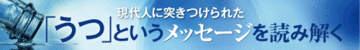
第9回
食事は私たちの生活の基盤をなすものですが、食生活にはその人の生活の様子が如実に反映してくるものです。毎日同じものを食べるなど、ガソリン補給のように「美味しさ」を求めずに「ただ食事をする」という人も案外少なくありません。今回は、食生活という観点から、現代人が陥りがちな不自然な状態について検討してみたいと思います。
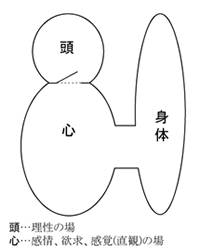
第8回
成果主義という人事評価システムが日本でも導入され、今日では多くの企業や組織でも用いられています。「タテ社会」の生んだ年功序列制の不公平感や理不尽さを払拭する合理的な方法として歓迎される一方、このシステムの問題点についても活発に議論されるようにもなってきました。生産率や効率性など「結果」を求めすぎて「質」を忘れがちになってしまっている人が多いようです。今回は、成果主義というシステムが人間の精神に及ぼすさまざまな影響について、掘り下げて考えてみたいと思います。
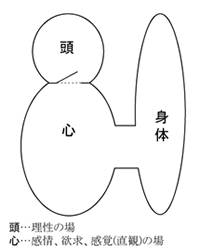
第7回
マニュアルは覚えられるのに、マニュアルのないことにはお手上げ。最近、いろいろな組織の中で、「自分で考える」力のない人が増加していることが問題になっているようです。「記憶力が良い」=「頭が良い」と思われがちですが、このように偏った「頭」の使い方ばかりしているうちに、「自分がわからない」といった行き詰まりに陥ってしまったケースが少なからず存在します。そこで今回は、「人間らしい思考力とはどういうものか?」というテーマについて考えてみたいと思います。
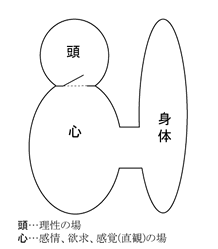
第6回
――私は、何をやっても長続きしないんです。若い世代を中心に、このような悩みを訴える方が少なくありませんが、特に自己愛(自分自身を愛すること)がうまくいっていない方たちによく見られる悩みでもあります。大概は、いわゆる「良い子」的な従順さと勤勉さの持久力を生んでいた「かりそめのモチベーション」であり、本人の意思に根差した「真のモチベーション」がつかめなくなってしまっているのです。
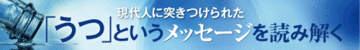
第5回
近年、報道により広く認知されるようになった「適応障害」は、ストレスに満ちた環境が原因で、抑うつや不安が生じ、仕事や学業に支障を来たします。今回は「適応」とは何かについて、掘り下げて考えてみます。
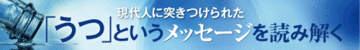
第4回
私たちは、「将来に備えて……」「もしものために……」といったフレーズが日常的に飛び交う中で暮らしています。しかし、このように将来への不安を回避しようと安定を志向するとき、人間は「今を生きる」ことから遠ざかってしまうという大きなジレンマを抱えてしまいます。今回は、このような安定や安全を志向する価値観に潜む問題点について考えてみたいと思います。
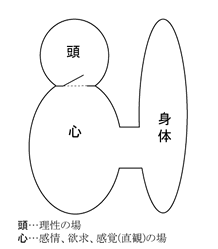
第3回
「なかなか寝つけない」「寝ても眠りが浅くて、疲れがとれない」「寝よう寝ようと思うと、よけい眠れなくなってしまう」…このような不眠症状は、「うつ」状態においてはもちろんのこと、精神的なバランスが乱れた場合に生じてくる、かなりポピュラーなものです。今回は、このように通常行なわれている薬物療法で見落とされがちなポイントについて、つまり、不眠という状態をどう捉えるべきなのか、不眠という症状からどんなメッセージが受け取れるのかといったことを考えてみたいと思います。
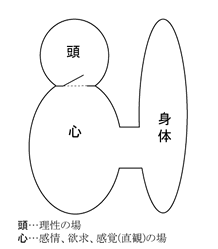
第2回
今の社会では、幼い頃から「やらなければならないこと」を休みなく課せられてくることが多く、なかなか、ゆっくりと「やりたいこと」に思いを巡らす余裕が与えられていません。人々の多くは、「自分は何をしたいのか?」「これは本当に自分がやりたいことなのか?」といった問いを持つこと自体に、不慣れになってしまっているようです。しかしながら、このように「主体」を見失ってしまったという悩みは、現代人のみに見られる新しいテーマというわけではありません。今回は、この苦悩に直面した代表的な人物として夏目漱石を参考にしながら、現代の私たちが、失われた「主体」をいかに回復できるかという問題について考えてみたいと思います。
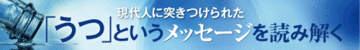
第1回
最近では社会的にもメンタルヘルスへの意識が高まっているが、依然として「うつ」に陥った人を取り巻く人間的環境は、まだまだ不十分。とりわけ、世代間のディスコミュニケーションが「うつ」についての無理解が生んでいる。――何不自由なく恵まれているはずなのに、何を悩むことがあるんだ? このような価値観を持つ上の世代から見れば、現代の若い世代の「うつ」の状態や引きこもり、ニートなどの状態は、まったく理解不能ということになるでしょう。今回は、このような世代間ディスコミュニケーションの背景に何があるのかということを、掘り下げて考えてみたいと思います。
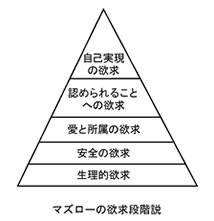
最終回
「うつは本当には治らない」「うつは再発しやすいものだ」といった認識が、依然として、あちらこちらでささやかれ、信じられているように見受けられます。これらは、「治る」ということを「元の状態に戻ること」と捉えて行なわれている治療のはらむ現実的な限界を多くの人が見て、流布されるに至った残念な風評です。repair(修理)ではなくreborn(生まれ直し)あるいはnewborn(新生)といった深い次元での変化こそが、真の「治癒」には欠かせません。この変化を「第2の誕生」と呼ぶことにしましょう。
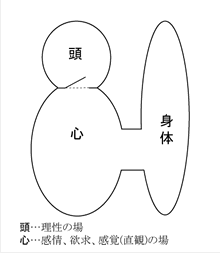
第23回
近年新しく「うつ」と呼ばれるようになった病態の中には、リストカッティング(手首自傷)などの自傷行為や、過食・嘔吐などの摂食障害を伴うタイプも存在します。今回は、こういった自傷行為や過食といった現象がなぜ起こるのか、また、そこから読み取るべきメッセージは何かといったことについて、考えてみたいと思います。
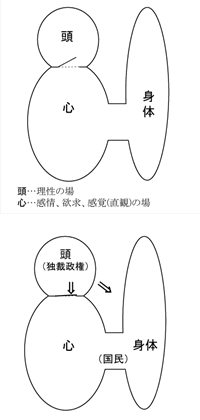
第22回
「努力することにこそ価値がある」という考え方は、私たち日本人の精神性に奥深く浸透しているものの1つです。しかし、「うつ」に苦しむ人々の多くは、元来、意志力の強いタイプで、発症以前には人並み以上に「努力」を重ねてきた歴史を持っているものです。意欲がなくなり活動性が低下してしまう「うつ」の症状は、「努力」に価値を置いて生きてきたことへの大きな反動、と見ることもできます。
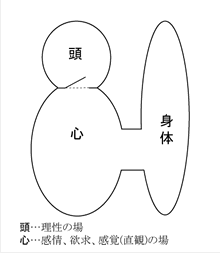
第21回
突然、強い不安とともに動悸や息苦しさ、冷汗、吐気などの発作(パニック発作)におそわれるパニック障害は、現代において「うつ」と同様、多くの方々が悩んでいる問題です。新しいタイプの「うつ」では、このパニック障害との境界線はかなり曖昧で、両者が合併していると診断されるケースもあれば、パニック障害から始まって後に「うつ」が徐々に現われてくるケースもあります。
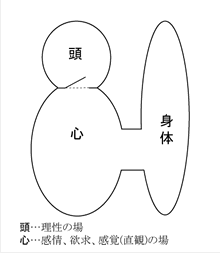
第20回
「自信が持てない」「自分のことが認められない」といった問題は、現代の「うつ」を考えるうえで、どうしても避けて通れない重要なテーマです。このような問題を抱えている方たちは、学業や仕事などで成果を上げて代償的に自己評価を維持しようと、無理を重ねがちです。しかし、この努力にはどうしても限界があって、ある時点でブレーカーが落ちたように「うつ」状態に陥ってしまうケースも少なくありません。今回は、この「自信」ということをめぐって考えてみましょう。