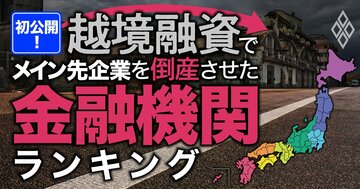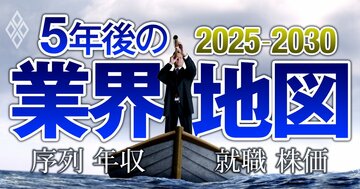「来なさそう」でも
誘い続けることが重要
次に重要なのは、孤立させないことです。ランチや雑談に気軽に誘ってみる。ただし、義務化してはいけません。
例えば、会社で毎月恒例の飲み会があるとしても、その人は絶対に来ないでしょう。ただ、来なさそうだからといって誘うのをやめるのではなく、一応、誘い続けることが重要です。
防衛機制が働いている場合、本人が自覚していないだけで、深層心理では行きたいと思っているからです。表面的には「飲み会なんてウザい」「キモい」という態度を取るかもしれませんが、それでも誘い続けるのです。
部下に対しては、問い詰めるのではなく、変化に関心を寄せることが大切です。「やる気はあるのか」と聞かれても、本人は「ないわけじゃないですよ」などと突っぱねるでしょう。「最近ちょっと疲れているみたいだけれど、気になることでもあるの」という聞き方をすることで、相手の防衛的な反応は和らぎます。
上司として必要なのは、本人の強みを思い出して言語化し、伝えてあげることです。
以前、本人にやる気があった時の仕事ぶりを具体的に思い起こし、「入社直後、あなたはすごく丁寧な仕事をしていたよね」「あのプロジェクトでの◯◯さんの工夫は今でも印象に残っているよ」といった具体的なフィードバックを通じて、「あなたは本来はできる人なのだ」ということを思い出させ、「そのことを、職場のみんなもわかっている」と陰に陽に伝えるのです。
本人も、「もうダメだ」という学習性無力感から立ち直って、自己効力感――「私にもできる」という感覚を少しずつ取り戻すことができます。
共感も大切です。「自分にも、昔、そういう時期ってやっぱりあったなぁ」といった話をしたり、「『モヤモヤ』している時って、なかなか動けないよね」と、相手の感情を理解しているという姿勢を示したりすることで、安心感を醸成していきます。
このような対応をすればいきなり本人の態度が変わるというわけではありません。しかし、こうした取り組みの中で、少しずつ本人の自己効力感が上がれば、孤立感が薄くなったり、前向きな発言が見られたりするようになったりと、変化の兆しが見えてくるはずです。
では、どのくらいの期間、周りは働きかけをしていくべきなのでしょうか。