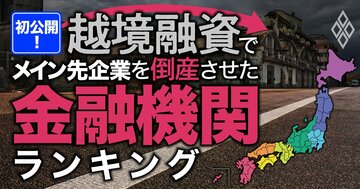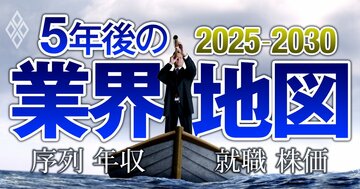静かな退職は甘えではない!?
「糾弾、無視、のけ者」は御法度
とはいえ、本人の中に「本当はもっと頑張りたい」「認められたい」という気持ちが残っており、完全にやる気を失ってはおらず、むしろその気持ちを守るために、表面的に無関心を装っているだけなら、本質的な問題は、現在の職場環境が若い人たちの成長欲求と承認欲求を適切に満たせていないことにあると言うこともできます。
もちろん全員が全員そうだとはいいませんが、彼らが求めているのは、単に楽をしたいということではなく、自分の価値を認めてもらい、成長できる環境なのではないでしょうか。
一定数の人が「静かな退職」を選んでいるのだとしたら、それをただ個人の怠惰や甘えの問題としてのみ片付けるのではなく、組織と個人の関係性における深刻なミスマッチの表れとして捉え、心の根源にある欲求を適切に満たすことが根本的な解決の近道になるでしょう。
上の世代は「なぜ機嫌を取るようなことをしなければならないのか」と思うかもしれませんが、当人に単純に「あなたは甘えているだけ」「やる気を出せ」と言っても効果がないどころか逆効果です。その背後にある動機を理解し、適切なアプローチを取ることが必要になります。
糾弾する、無視する、のけ者にするなどもご法度です。このような行動に出てしまうと、問題がエスカレートし、静かな退職が「騒がしい退職」に発展するリスクがあります。
「静かな退職者」が、問題を起こして辞めたり、ハラスメントやいじめがあったと訴訟を起こしたりする事態を招くということです。これは決して得策ではありません。
静かな退職者への対応として重要なのは、心理的安全性の確保です。そして、それは上司だけが作るものではなく、職場の雰囲気そのものを、メンバー全員で改善していく必要があります。
ここは、周囲の人も上司も、「一言言いたくなる気持ち」をぐっと堪え、本人を責めるのではなく、なぜそうなったのかという背景に丁寧に向き合いながら、頑なになっている静かな退職者の心を解きほぐしていくことが大切です。
具体的には、「もっと頑張って!」などと無理に明るく励まさないこと。「昔一緒にやったプロジェクトみたいなことを、また一緒にやれるといいね」というようにまずは温かい言葉をかけるだけで十分です。
「いつでも話を聞くよ」といったオープンな働きかけも重要です。周囲の人たちは温かく見守るという姿勢、本人を認めるというスタンスがポイントになります。