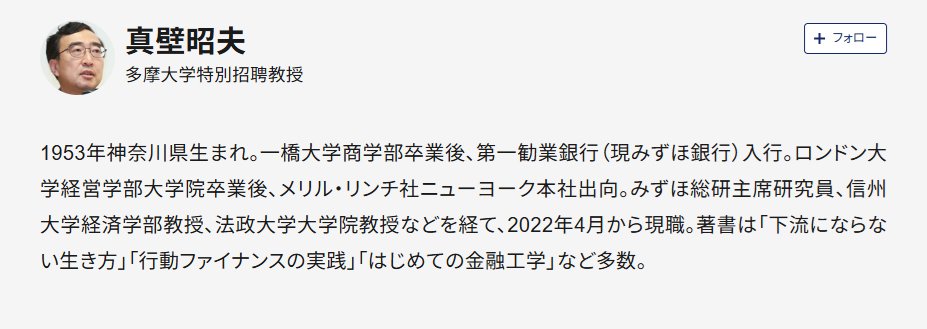懸念されるわが国の
自動車メーカーの対応力
ドイツでは、防衛大手のラインメタルがフォルクスワーゲンの工場を買収し、戦車の生産能力増強を検討しているとの報道もあった。自動車企業の合従連衡は、ソフトウエアや半導体などのIT先端企業だけでなく、防衛など非自動車業界を巻き込みながら進んでいる。
そこで問われるのは、わが国の企業がいかに再編に対応できるかだ。現状を見る限り、わが国の自動車関連企業に不透明な部分は多い。一部では、トヨタですら、ソフトウエア重視の戦略実行が難しいとの見方もある。
ホンダは米国で日産から乗用車の供給を受け、自社ブランドで販売することを検討しているという。それは両社の生き残りに有効な取り組みなのだろうが、いかんせんスピード感が伴わない。
日産の事業戦略を見ると、このままでは資産売却や人員削減を余儀なくされており、自力再建の戦略は後手に回っている。主力の追浜工場が閉鎖されると、京浜工業地帯の活力は停滞し、わが国の経済成長率の下振れ懸念も高まる。
企業が社会の公器であることを考えると、日産は迅速に再建に向けた有効な戦略を打ち出す必要があるのだが、今のところ、なかなか実態が伴っていない。台湾のホンハイなどが、日産、さらにはホンダにも、より広範囲な協業を提案する可能性が高まっているとみられる。
マツダやスバルの事業戦略もやや気がかりだ。これまで、マツダは対米輸出を増やして収益を上げてきた。自動車関税が15%になったことで、いったん、同社の株価は反発したが、その先の戦略がはっきりしない。
8月以降、米国の新車の価格は上昇し、労働市場の減速の影響から販売は鈍化し、いずれ減少が鮮明化するとの見方もある。もしそうした状況が発生すると、トヨタといえども、収益力を維持することは容易ではないかもしれない。
現状を見る限り、わが国の自動車産企業がグローバルな合従連衡を主導するとは考えづらい。ただ、対応が遅れると、わが国の自動車関連企業が新興国のIT、電子機器受託製造、自動車メーカーなどの買収対象になる可能性もある。今すぐではないかもしれないが、わが国の基幹産業である自動車メーカーの競争力が低下し、経済全体に重大なマイナスのインパクトが波及するリスクは上昇しているとみた方がよいだろう。