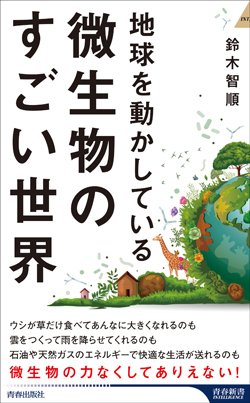微生物は棲みやすい場所と草というエサを手に入れて、ウシは草を消化してもらって栄養を手に入れるという、共生関係を築いているわけです。
第2胃は蜂巣胃(はちのすい/ほうそうい)〈焼き肉のハチノス〉といい、ポンプの役割をして第1胃に草を出し戻したり、食道に押し出したりする役割をします。ウシはよくモグモグと口を動かす反芻(はんすう)という行動をしていますが、これは口まで押し出されて戻ってきた草をまた噛んでいるのです。
次の第3胃は葉状胃(ようじょうい)〈重弁胃(じゅうべんい)ともいい、焼き肉のセンマイ〉といいます。葉状胃にはたくさんのヒダがあり、このヒダの間に草が挟まることで、胃壁から草の水分と栄養素を吸収しやすくしています。
最後の第4胃は皺胃(しわい/しゅうい)〈焼き肉のギアラ〉といい、ヒトと同じく消化吸収する機能を持つ胃です。ここではじめて消化液の胃酸が出て最終的な消化をします。
しかし、胃酸が出るということは、酸により微生物が殺されてしまうということです。ここまでウシの消化分解を助けてくれた微生物ですが、皺胃にたどり着いた後は、ここで一生を終えてしまいます。そして、微生物は消化され、タンパク質などのウシの栄養になるのです。
この微生物を消化吸収してつくられるタンパク質が、あの大きなウシの筋肉や臓器、皮膚などの体をつくるために重要な役割をしているのです。
つまり、ウシが草だけであの大きな体を保つことができるのは、微生物がつくる代謝物と、微生物自身とが栄養となってウシを支えているからです。
こうして見てくると、ヒトも動物も自分たちだけでは生きていくことができない、ということが見えてきます。目には見えない無数の微生物たちが、それぞれの役割を果たしながら、私たちの暮らしを静かに、でも確実に支えてくれているのです。