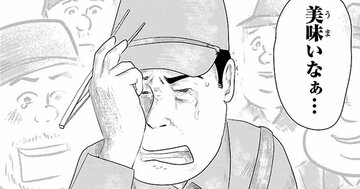前線部隊に届く軍需品の割合は
45年には51%にまで低下
このような多数の餓死者を出した最大の原因は、制海・制空権の喪失によって、各地で日本軍の補給路が完全に寸断され深刻な食糧不足が発生したからである。
前線部隊に無事に到着した軍需品の割合(安着率)は、1942年の96%が、43年には83%に、44年には67%に、さらに45年には51%にまで低下し、海上輸送された食糧の三分の一から半分が失われた。積み出した軍需品の量自体が現地軍の要求を大きく下まわる状況下での安着率のこの低下である(『太平洋戦争喪われた日本船舶の記録』)。
マラリアにかかると体力が弱まり
食糧不足で極度の栄養失調になり死亡する
問題は、栄養失調が前線での疾病と相互に関連していたことである。陸軍主計中佐の田村幸雄は、すでに1943年8月の段階で、「第一線における疾病は栄養の失調が最も大なる原因の一つとなって」いたと指摘している(「第一線における戦力増強と給養」)。
また佐世保鎮守府第六特別陸戦隊の部隊史は、栄養失調とマラリアの関係について次のように記している。
〈〔1944年〕4月ごろから急に栄養失調症が増えてき、栄養失調による死者、すなわち餓死者が出始めた。マラリアにかかると40度の高熱が出てそれが一週間ぐらいつづく。それで体力が弱まったところへ食糧がなく、極度の栄養失調に陥って、その後は、薬も食事も、ぜんぜん受け付けない状態になって死んでゆく――それが典型的な餓死のコースだった。諸病の根源は、食糧不足だった。(『ソロモンの陸戦隊 佐世保鎮守府第六特別陸戦隊戦記』)〉
米軍はDDTの大量使用によってマラリア原虫を媒介する蚊を駆除し、予防に成功した。だが日本軍の場合、マラリア研究自体はかなり進んでいたもののその対策面で大きく立ち遅れたため、特に南方戦線ではマラリアが猛威を振るった(『マラリアと帝国』)。
日中戦争初期から現れ、
「戦争栄養失調症」と称された病気とは
栄養失調の問題で重要なのは、戦争神経症とも関連する戦争栄養失調症である。
この病気はすでに日中戦争初期から現われていた。1938年4~6月の徐州作戦に従事した兵士のなかから、極度の痩(や)せ、食欲不振、貧血、慢性下痢などを主症とする患者が多発した。治療はきわめて困難で死亡に至るケースが多かった。