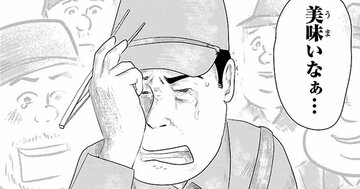出所:貴志俊彦『戦争特派員は見た 知られざる日本軍の現実』(講談社現代新書)表紙より/上海戦線:羅店前面の突撃(松尾邦蔵撮影)(出典:毎日戦中写真)
出所:貴志俊彦『戦争特派員は見た 知られざる日本軍の現実』(講談社現代新書)表紙より/上海戦線:羅店前面の突撃(松尾邦蔵撮影)(出典:毎日戦中写真)
戦後80年の今夏、第二次世界大戦について改めて振り返りたい。従軍従軍特派員が残した写真を手がかりに、戦争の実像をたどる。※本稿は、貴志俊彦『戦争特派員は見た 知られざる日本軍の現実』(講談社現代新書)の一部を抜粋・編集したものです。
戦時の様子を撮影した
戦争特派員たち
戦後80年――私たちは戦争の姿をどれだけ知っているだろうか。
じつは、日本各地の新聞社や通信社は、物資の不足、軍の廃棄命令、空襲、GHQによる接収といった四大要因によって、戦時中に撮った写真を残せなかった。毎日新聞東京本社(旧・東京日日=以下、「東日」と略)でさえ、「終戦」の際に所蔵していた写真を焼却した。
だが、毎日新聞大阪本社(旧・大阪毎日=以下、「大毎(だいまい)」と略)が秘蔵してきた毎日戦中写真には珍しくも、戦争特派員たちの姿を撮った写真400点あまりが残されており、彼らが軍と共に戦火の中でどのように生き抜いたかを知る手がかりを与えてくれる。
軍人ではなく、戦争の現場にいたもうひとりの人間の視線がそこに残されていたのである。
「不許可」とされた写真は
何を隠蔽しようとしたのか
毎日戦中写真には、「不許可」とされた写真が少なからず含まれている。社内外での検閲を通じて、大毎・東日が報道できなかった/しなかった写真とは、どのようなものだったのか。「不許可」とされた写真/撮られなかった写真に内在する隠蔽(いんぺい)された事実を精査し、視覚的記録として抹消された情報を再構築することを試みる。
大毎・東日では、外地の特派員たちが撮影したオリジナルネガが、連絡船や空輸で大阪本社に運ばれて保管された。
一般には、このネガを大毎写真部で現像、焼き増しして、大阪、東京、西部、中部の編集局に各一枚、陸軍省または海軍省、内務省、内閣情報部に各一枚が、列車便などを使って送られた。毎日戦中写真に関する限りだが、憲兵隊や特別高等警察(特高)の検閲を受けた跡は見つからない。
ただし、日本本土に向けて写真が送付される前に、すでに海外の現地機関で検閲がおこなわれていたことには注意する必要がある。明治期から、内地、外地を問わず、各地の要塞(ようさい)司令部が写真や絵葉書などを検閲していたことは、よく知られている。
増えていく検閲機関
一時的に使用禁止にする「保留」も
1930年代以降になると、検閲機関も多様になっていく。支那派遣軍や関東軍、台湾軍、南方軍など、軍部の検閲が増えたのである。
新聞社内では、送られてきたネガを密着写真や焼付写真に現像して、これを写真台帳に貼り付けて整理していた。写真台帳には、青い印で写真部が受理した日付が押されていたり、撮影月日、場所、撮影者などのメモが書かれたりしている。
とりわけ重要であったのが、東京本社からの連絡により、写真使用が許可されない場合は「不許可」の赤い印、許可であれば「陸軍省検閲済」「海軍省許可済」「情報局検閲済」などの赤い印が、それぞれ社内で写真を整理するなかで押されていることである。
その他、「保留」などの印が押されて、許可が出るまで一時的に使用禁止とする場合もあった。