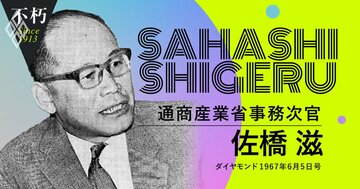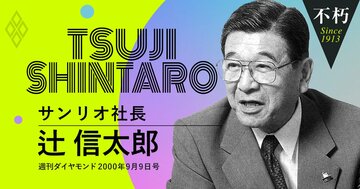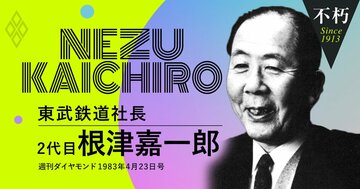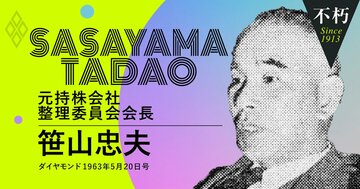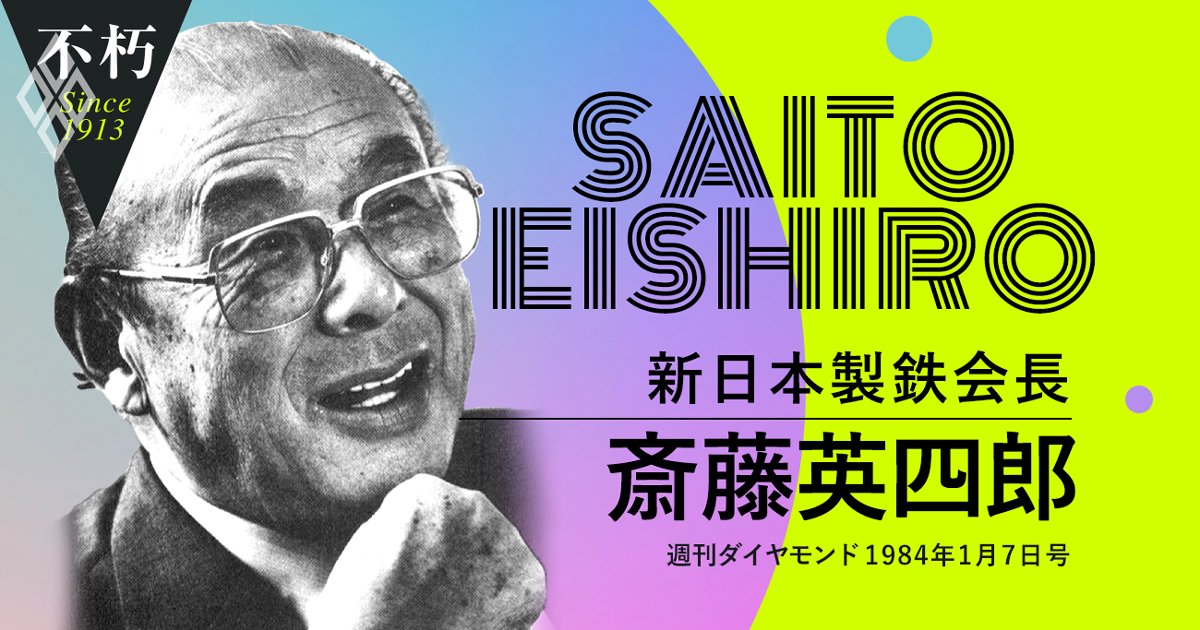
1984年1月7日号に掲載された新日本製鉄会長・斎藤英四郎(1911年11月22日~2002年4月22日)へのインタビュー記事だ。
斎藤は当時、日本プロジェクト産業協議会(JAPIC)の会長を務めており、都市開発や交通インフラのような巨大プロジェクトに民間の活力を導入するという方針を掲げていた。インタビューのリード文で本誌聞き手は、「民間の活力とは平たくいえば民間の金を使って採算的にやるということだ。東北新幹線や青函トンネルをみれば空おそろしくなるような話ではないか」と、若干の懸念を示している。
しかし斎藤は、公共投資に民間資金を活用することは特別なことではなく、国民が生み出した資金の使い方の違いにすぎないと指摘。採算性とリスク保証が不可欠であり、長期的視点での国土開発やインフラ整備の重要性を強調する。
例に挙げているのは82年に開通したばかりの東北新幹線だ。当時の日本は、高度成長期を終えて成熟社会を迎えており、財政赤字や地方格差、インフラ老朽化など新たな課題に直面していた。斎藤の「公共投資に民間資金を活用するのは特別なことではない」という発言は、資金の本質的な流れを見抜いたものといえる。国民の貯蓄や税金が最終的に社会インフラに還元されるという視点は、現代の官民連携(PPP)やサステナブル投資の考え方にも通じるものだ。
また、採算性とリスク保証を重視する姿勢は、始まりつつあったバブル経済の過熱や無駄な公共事業への警鐘とも受け取れ、経済合理性と公共性のバランスを求めるものでもある。長期的な国土開発やインフラ整備の重要性を説く点は、地方活性化や将来の産業基盤強化を見据えたもので、当時の「東京一極集中」や「地方衰退」への問題意識も反映している。
さらに後半では、軽薄短小(先端・ソフト産業)と重化学工業の連携が今後の日本経済の発展に不可欠であり、バランスの取れた経営思考が求められると述べている。これも、デジタル化が進む現代にも通じる普遍的な経営観といえる。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
斎藤は当時、日本プロジェクト産業協議会(JAPIC)の会長を務めており、都市開発や交通インフラのような巨大プロジェクトに民間の活力を導入するという方針を掲げていた。インタビューのリード文で本誌聞き手は、「民間の活力とは平たくいえば民間の金を使って採算的にやるということだ。東北新幹線や青函トンネルをみれば空おそろしくなるような話ではないか」と、若干の懸念を示している。
しかし斎藤は、公共投資に民間資金を活用することは特別なことではなく、国民が生み出した資金の使い方の違いにすぎないと指摘。採算性とリスク保証が不可欠であり、長期的視点での国土開発やインフラ整備の重要性を強調する。
例に挙げているのは82年に開通したばかりの東北新幹線だ。当時の日本は、高度成長期を終えて成熟社会を迎えており、財政赤字や地方格差、インフラ老朽化など新たな課題に直面していた。斎藤の「公共投資に民間資金を活用するのは特別なことではない」という発言は、資金の本質的な流れを見抜いたものといえる。国民の貯蓄や税金が最終的に社会インフラに還元されるという視点は、現代の官民連携(PPP)やサステナブル投資の考え方にも通じるものだ。
また、採算性とリスク保証を重視する姿勢は、始まりつつあったバブル経済の過熱や無駄な公共事業への警鐘とも受け取れ、経済合理性と公共性のバランスを求めるものでもある。長期的な国土開発やインフラ整備の重要性を説く点は、地方活性化や将来の産業基盤強化を見据えたもので、当時の「東京一極集中」や「地方衰退」への問題意識も反映している。
さらに後半では、軽薄短小(先端・ソフト産業)と重化学工業の連携が今後の日本経済の発展に不可欠であり、バランスの取れた経営思考が求められると述べている。これも、デジタル化が進む現代にも通じる普遍的な経営観といえる。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
公共投融資に民間資金を使う以上
必ず採算性が要求される
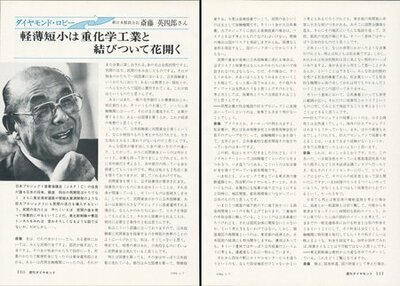 1984年1月7日号より
1984年1月7日号より
金は、誰の金かといったら、ある意味においては、みんな民間の金ですよ。国民が稼ぎ出した金ですよ。その金が税金のかたちで政府にいき、貯蓄のかたちで郵便貯金になったのは資金運用部に回る。あるいは民間金融機関にいったのは、それがまた企業に貸し出される。金の元は全部民間ですよ。民間の活力、民間の生み出したものですよ。それが税金のかたちで一回国庫に入ると、公共投融資というかたちに出たり、あるいは教育とか、福祉とか、いろんなかたちで国民に還付されてくる。これが政治というものだと思うんです。
あるいはまた、一般の市中銀行とか農業組合とか、相互銀行とか、そういうものを通じて、いったん金融機関に入って、それがまた還流されて、企業が借りるとか、あるいは国債を買うとか、これが経済の実態だと思うんです。
従って、公共投融資に民間資金を使うというと、なにか特別のものと考えがちだけれども、大きな流れを見ると、変わりがないものだと思うんです。みんな国民が稼ぎ出した金の使い方だけの違いで、従って、仮に民間資金というのは何かというと、企業も持っておりましょうけれども、仮に市中銀行を考えると、市中銀行の持っている金を投資してもらうわけです。例えば私ども2兆近く金を借りておりますが、貸してくれるわけですね。