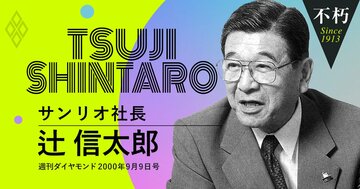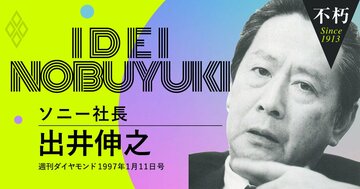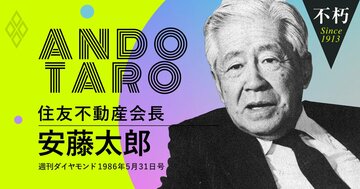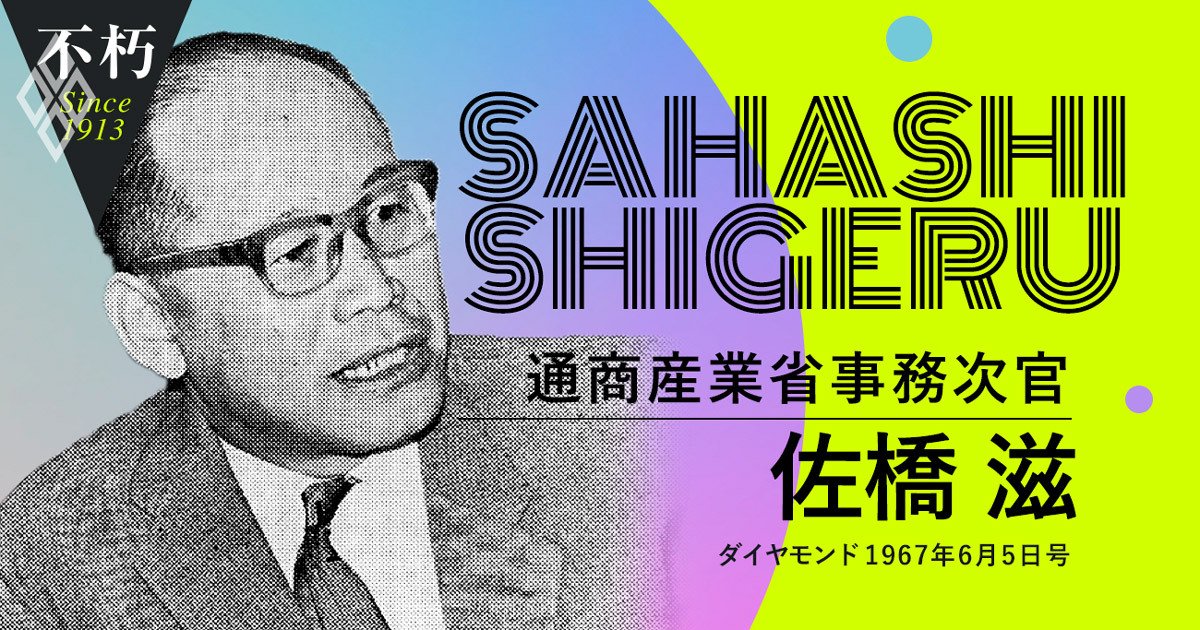
佐橋滋(1913年4月5日~1993年5月31日)は、昭和の通商産業省(現経済産業省)で事務次官を務めた名物官僚だ。1960年代の資本自由化の波に対し、強いナショナリズムの立場から警鐘を鳴らし続け、城山三郎の経済小説『官僚たちの夏』で主人公のモデルにもなった。
1966年4月に退官するが、その直後の1967年6月5日号に佐橋のインタビューが掲載されている。1960年代の日本は、戦後の経済復興と国際化の中で、外国からの資本流入が大きなテーマとなっており、1967年7月から資本自由化が部分的に実施され、徐々に拡大されていく過程にあった。
佐橋の持論は、官民協調方式で国際競争力を確保することで、資本自由化に備えよというものである。特に自動車産業に対しては、完成車メーカーが10社もひしめいている現状に「3社程度で十分」、企業統合を促す発言をして物議を醸していた。この記事でも、自動車産業とは、鉄鋼・機械・電装といった複合的要素を内包する「総合機械産業」であり、日本の国際収支を支える戦略的基幹産業であると語り、そのためには再編と合理化が不可欠だと説いている。軽四輪のような保護された領域での収益を頼みに大衆車市場に乱立する姿勢を、「戦略産業としての自覚に欠ける」とまで厳しく批判する。
加えて、資本自由化に伴う外資導入に対しては、「ナショナリズムを抜きに自由化を語るのはナンセンス」と断言。たとえ一部の外資導入が認められるとしても、核心的な産業が外国資本に握られる事態は、主権国家としての自立性を失う危険を孕むと警告していた。
「日産なり、トヨタなりが外資に取られでもしたら大問題」と佐橋は語っているが、実際、その懸念は現実のものとなった。1999年、経営危機に陥った日産自動車はフランスのルノー傘下に入り、名目上は「国産企業」でありながら、実質的には外資系の経営方針のもとで運営されることとなった。この構図こそ、佐橋が憂慮した“国のかたち”の変質に他ならない。
佐橋は、自動車産業が外資に「乗っ取られ」ることで、日本人が単なる使用人に成り下がり、将来世代に「あの時代の日本人はどうかしていた」と嘲られることを恐れた。「所得さえ上がればいい」「車が安く買えればそれでいい」という経済生活至上主義を、本質的な国力の空洞化だと捉えているのである。
グローバリズムが進行する現代においても、「国際化(インターナショナル)」の根底には「ナショナル」が必要だという佐橋の主張、経済合理性よりも国家の戦略的利益を優先する姿勢は、「アメリカ第一主義」を掲げ、自動車や鉄鋼に対する高関税政策を通じて国内産業の防衛に乗り出す現代の米トランプ政権とも重なるところがある。(文中敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
1966年4月に退官するが、その直後の1967年6月5日号に佐橋のインタビューが掲載されている。1960年代の日本は、戦後の経済復興と国際化の中で、外国からの資本流入が大きなテーマとなっており、1967年7月から資本自由化が部分的に実施され、徐々に拡大されていく過程にあった。
佐橋の持論は、官民協調方式で国際競争力を確保することで、資本自由化に備えよというものである。特に自動車産業に対しては、完成車メーカーが10社もひしめいている現状に「3社程度で十分」、企業統合を促す発言をして物議を醸していた。この記事でも、自動車産業とは、鉄鋼・機械・電装といった複合的要素を内包する「総合機械産業」であり、日本の国際収支を支える戦略的基幹産業であると語り、そのためには再編と合理化が不可欠だと説いている。軽四輪のような保護された領域での収益を頼みに大衆車市場に乱立する姿勢を、「戦略産業としての自覚に欠ける」とまで厳しく批判する。
加えて、資本自由化に伴う外資導入に対しては、「ナショナリズムを抜きに自由化を語るのはナンセンス」と断言。たとえ一部の外資導入が認められるとしても、核心的な産業が外国資本に握られる事態は、主権国家としての自立性を失う危険を孕むと警告していた。
「日産なり、トヨタなりが外資に取られでもしたら大問題」と佐橋は語っているが、実際、その懸念は現実のものとなった。1999年、経営危機に陥った日産自動車はフランスのルノー傘下に入り、名目上は「国産企業」でありながら、実質的には外資系の経営方針のもとで運営されることとなった。この構図こそ、佐橋が憂慮した“国のかたち”の変質に他ならない。
佐橋は、自動車産業が外資に「乗っ取られ」ることで、日本人が単なる使用人に成り下がり、将来世代に「あの時代の日本人はどうかしていた」と嘲られることを恐れた。「所得さえ上がればいい」「車が安く買えればそれでいい」という経済生活至上主義を、本質的な国力の空洞化だと捉えているのである。
グローバリズムが進行する現代においても、「国際化(インターナショナル)」の根底には「ナショナル」が必要だという佐橋の主張、経済合理性よりも国家の戦略的利益を優先する姿勢は、「アメリカ第一主義」を掲げ、自動車や鉄鋼に対する高関税政策を通じて国内産業の防衛に乗り出す現代の米トランプ政権とも重なるところがある。(文中敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
自動車産業は総合機械産業
戦略産業としての自覚を持て
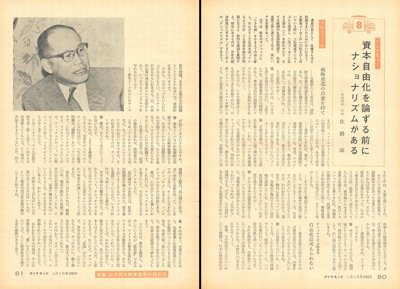 1967年6月5日号より
1967年6月5日号より
――自動車という商品は、国際的な規模の利益を追求すべきである。が、これを確立するのに自由競争で勝負を決めていたのでは、とても資本自由化に間に合わない。再編成をやれ、というご意見ですが……。
自由化というのは、いつまでも待てる筋合いではない、と思うんです。自動車業界だけの問題ではなく、資本自由化が消費者のプラスになるという大原則があるわけですから……。
それなのに、いまの業界はとても自由化できる状態ではない。日産・プリンス、トヨタ・日野のように、ある程度の再編成は進んできたが、ニューエントリーというか軽四輪メーカーが小型車の分野に入ってくるのは、あまり好ましい状態ではないと思うんです。