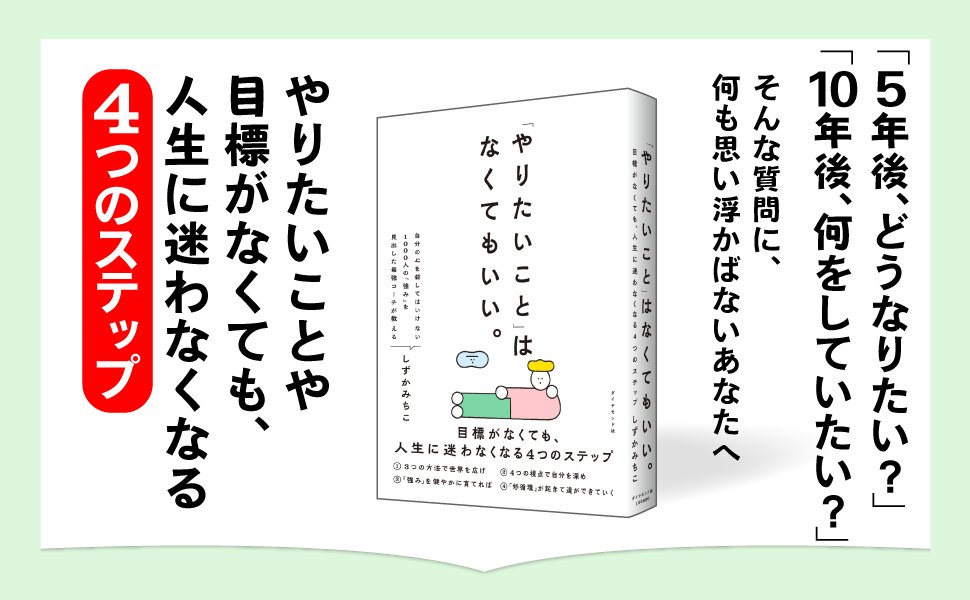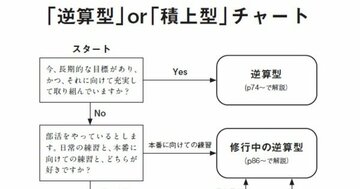社会的な「成功レール」の崩壊、どんどん不確実になる未来、SNSにあふれる他人の「キラキラ」…。そんな中で、自分の「やりたいこと」がわからず戸惑う人が、世代を問わず増えています。本連載は、『「やりたいこと」はなくてもいい。』(ダイヤモンド社刊)の著者・しずかみちこさんが、やりたいことを無理に探さなくても、日々が充実し、迷いがなくなり、自分らしい「道」が自然に見えてくる方法を、本書から編集・抜粋して紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
やりたいことがないなら、とりあえずこれを!
本書では、「やりたいことがない人」が無理に目標を見つけなくても自然に道が見えてくるための最初のステップとして、世界の仕組みを知ることをおすすめしています。大きくは「人間の仕組み」と「お金の仕組み」です。今回は「お金の仕組み」を知るために、学んでおくとよい具体的な内容をお伝えします。
1 「簿記」を学ぶと世界の「二面性」や「バランス」が理解できるように
日本の一般的な簿記資格(日商簿記、全経簿記、全商簿記)で扱われている複式簿記は、13世紀前後にイタリアで考案されて以来、世界中で使われ続けている世界共通の普遍的な仕組みです。
複式簿記の特徴は、全ての取引を必ず二面性で捉えることにあります。
例えば、現金100万円を人から借りた場合、確かに手元にお金は増えますが、同時に借金の返済の義務も生まれます。
また、「価値」の考え方もわかるようになります。商品を100万円で仕入れた場合、商品という物は増えますが、その代わりに銀行残高が100万円減ったり借金が増えたりと、全体で所有している価値の総量は変化しません。
簿記とはこの「価値の移動」を記録する仕組みなのです。増えるものと減るものが常にバランスを保ち、全ての取引に二面性があることを理解すると、目の前の現象だけでなく、その裏側で何が起きているのかを考えられるようになります。
社会で起きる様々な経済現象にも、この「二面性」と「バランス」が存在しています。表面的に見ると、一方だけが得をしたり損をしたりしているように見えても、裏では必ず価値の交換が行われていると考える習慣を身に付けることで、見逃していたものが見えるようになってきます。
簿記の二面性とバランスを学ぶ目的であれば、日商簿記3級で十分でしょう。もし物を作って販売するなどしたい場合は、日商簿記2級から範囲に入る工業簿記を学ぶと、原価の概念が理解できるのでおすすめです。
2 「FP」資格の勉強は人生の場面ごとのお金の知識が身につく
FP(ファイナンシャル・プランナー)の資格を通じて学べるのは、人生の様々な場面でのお金との付き合い方。FP3級で、個人の人生に関わるお金の知識を得ることができ、FP2級では、3級の知識を深く知ることに加え、事業をやるときに知っておくといいお金の知識が加わります。
FPの特徴は、人生の重要な場面ごとに必要となる知識を網羅して学べることです。例えば、会社で働くなら給与や退職金、社会保険の扱いを知っておくと損することがないでしょう。
給与をもらうときには税金の話が出てくるし、老後資金を考えると投資が視野に入ります。家族ができたら万一のための生命保険の検討もしておいたほうが安心だし、親の介護が始まれば介護保険にお世話になります。このように、生きていると発生するお金に関するあれこれを一通り学ぶことができるので自分の人生に役立ちます。
お金に関する制度については、どのようなものがあるかだけでも知っておくと、万が一のときに安心です。法律や制度の改正は毎年のように行われるため、どういった改正が行われたかを知ることで、政府が国民に対してどういう考えを持っているのかも理解することができます。
なお、FPの試験に合格するためには細かい税率や金額などの数字を暗記する必要がありますが、それらは毎年のように変更されるので、合格を目指すのではなく、仕組みを知るためだけに勉強するなら記憶する必要はありません。
計算も苦手なら、できなくても大丈夫。大切なのは、どのような制度があるかを知り、基本的な考え方を理解することです。制度が存在することさえ知っていれば、いざというときに調べたり人に相談したりできます。控除の仕組みや課税の原則などの基本的な考え方は簡単には変わらないので、仕組みがわかっていれば活用できるようになります。
*本記事は、しずかみちこ著『「やりたいこと」はなくてもいい。 目標がなくても人生に迷わなくなる4つのステップ』(ダイヤモンド社刊)から抜粋・編集したものです。