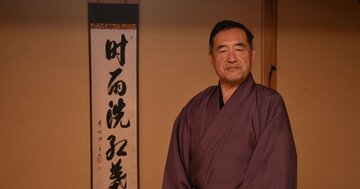そして、現在の茶道の基礎が築かれたのは室町時代。この時代に、村田珠光(むらたじゅこう)によって、「わび茶」という質素で静かな美しさを重視した茶道の形が生み出されました。
その後、千利休が「和敬清寂」という茶道の基本理念を確立し、茶道を完成させました。
茶道では、この「和敬清寂」という四つの精神が重視されています。
和(わ):お互いの調和を大切にし、穏やかな空間を作り出すこと。
敬(けい):相手を敬い、礼儀を尽くすこと。
清(せい):心を清らかに保つこと。
寂(じゃく):静けさのなかで心の安らぎや落ち着きを見つけること。
これらを実践することで、茶道はただお茶を飲むだけではない、深い意味を持つものとなります。茶道の目的は、静かで落ち着いた時間を過ごし、心の平穏を得ることにあるのです。
心を軽やかにしてくれる小さな習慣
私たちは日々、忙しい生活のなかで身体を酷使し、心を休める時間をつい後回しにしがちです。スマホを見ている時間は増えても、自分の心と向き合う時間はどれくらいありますか?
心の健康は身体の健康と同じくらい大切ですが、心はどのように整えればいいのでしょうか? 心の整え方がわからない人におすすめしたいのが茶道です。
茶道は、心のストレッチのようなもの。身体のストレッチが筋肉をほぐし、柔軟性を高めるのと同じように、心のストレッチは、心の緊張を解きほぐし、柔らかくしなやかにします。
心が固くなるとストレスに耐えられなくなり、視野が狭くなることがあります。しかし、心にストレッチを加えることで、余裕が生まれ、より豊かな生活を送ることができます。先述した通り、茶道は難しいものではありません。本来の茶道は、もっとやさしくて、日常に寄り添ったもの。なぜなら茶道の根底にあるのは、心を込めて、一碗のお茶を差し上げること。ただそれだけだからです。
むしろ、一碗のお茶を楽しむという誰でも簡単に始められるものです。みなさんもお茶を口にしたときに、ほっとした経験はありませんか? そのほっとして心がほぐれるひとときが、心の緊張をほどいてくれるのです。