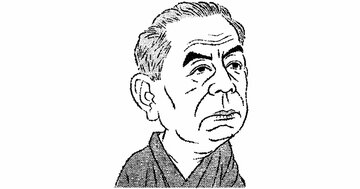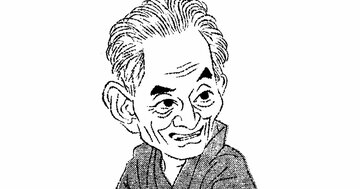「原稿を書いてくれない…」ならどうする?“逆転の発想”に学ぶ課題解決のヒント
文芸作品を読むのが苦手でも大丈夫……眠れなくなるほど面白い文豪42人の生き様。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、名前は知っていても、実は作品を読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文芸作品が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。ヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を大公開!
※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。
 イラスト:塩井浩平
イラスト:塩井浩平
大ヒット作『真珠夫人』作者
マルチな才能に驚愕
雑誌の常識を変えた、菊池寛の2つの発明
実は、菊池が『文藝春秋』で発明したことが、2つあります。
1つは「座談会記事」です。いまでは複数人が集まって特定のテーマについて議論する座談会を記事にして雑誌に掲載するのは、ごく当たり前になっていますが、このスタイルを確立したのは菊池なのです。
“書いてもらう”から“しゃべってもらう”へ
とはいうものの、これはいわば“苦肉の計”でした。原稿を依頼しても執筆を拒むことのある高名な作家たちに、気軽に発言してもらうための策だったのです。
菊池の手口はこうです。
作家たちを料亭に呼び、高級な料理と酒でもてなして、「どうぞ勝手にしゃべってください」と促します。当時は小型の携帯録音機はありませんでしたから、話す内容をその場で記者が速記して、あとで記事にまとめるのです。
芥川も座談会に呼び出されて「俺、何もしゃべることないよ」などとごねたこともありましたが、菊池は「適当に飲み食いして、しゃべってくれればそれでいいよ」といなしたそうです。
まったく菊池というのは、つくづく人心掌握術に長けた人物なのでしょう。
元祖“文春砲”、その誕生秘話
もう1つの発明は、「ゴシップ記事」です。
いまでは『週刊文春』が著名人のスキャンダルやスクープをとり上げ、“文春砲”などと呼ばれていますが、「ゴシップ記事」を流行させたのは菊池なのです。
『文藝春秋』で最初に扱ったのは、作家のゴシップ記事でした。刊行の翌年、大正13(1924)年2月号で、「文壇諸家価値調査票」という企画を掲載したのです。
文豪たちを丸裸に?愛と皮肉の通信簿
学校の成績表のように、文壇の作家たちのあれこれを採点するという“皮肉を込めたゴシップ記事”です。
芥川龍之介、有島生馬、泉鏡花……と作家を並べ、「学殖(学問の素養)」「天分(天から与えられた才能)」「修養(養い蓄えている教養)」「度胸」「風采(容姿・態度など見かけ上の様子)」「人気」「資産」「腕力」「性欲」「好きな女」「未来」と11項目にわたり、独断と偏見を交えたような採点を掲載しています。
「大正十三年十月末現在」と正確性を期すような但し書きがある半面、「例により誤植多かるべし」と自虐的なエクスキューズも交えており、ユーモアたっぷりで笑いを誘います。
また、点数の目安として、「六十点以上及第」「六十点以下五十点までを仮及第」「八十点以上優等」としています。
天才・芥川龍之介への手厳しい評価
たとえば、芥川龍之介は「学殖 九六」「天分 九六」「修養 九八」「度胸六二」「風采 九〇」「人気 八〇」「資産 骨とう」「腕力 〇」「性欲 二〇」「好きな女 何んでも」「未来 九七」とあります。
総じて高得点のなか、「腕力0点」「好きな女 何んでも」と、ひどい言われようです。
このころの作家たちは、いまでいう「インフルエンサー」的な立場にあったこともあり、一般大衆からの注目度も高かったので、この企画は大きな反響を得ました。