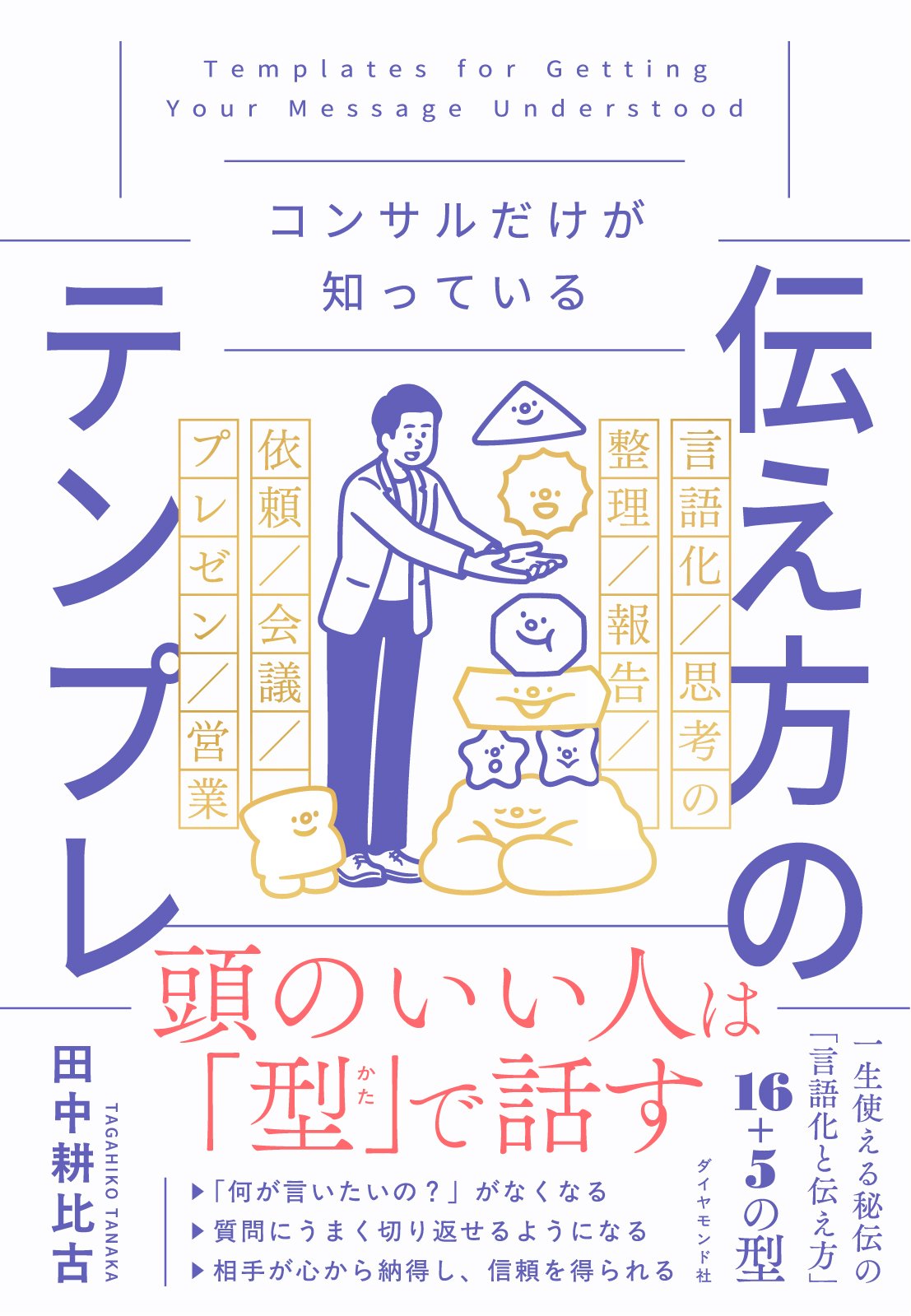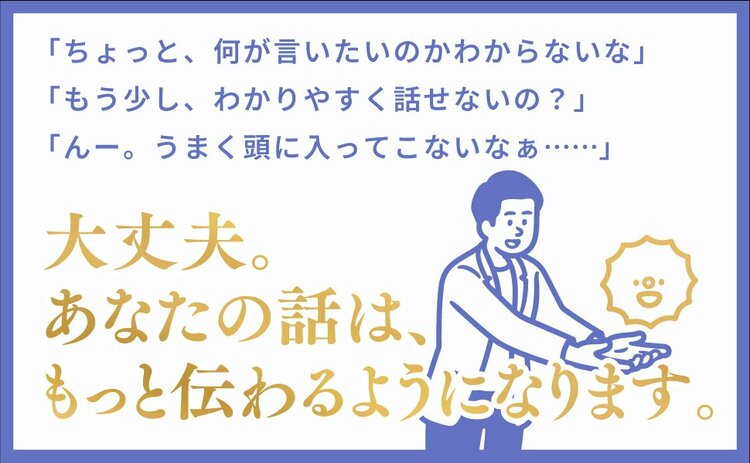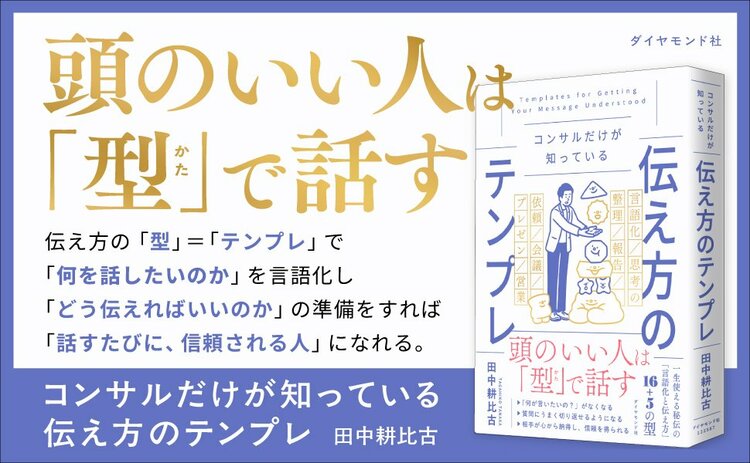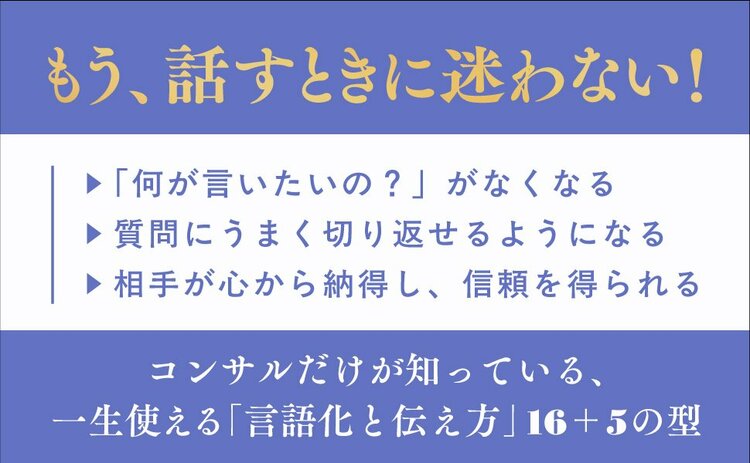「主観→客観テンプレ」の3ステップ
ステップ①:主観を書き出す
最初に、自分の考えていることを書き出します。
「主観→客観テンプレ」では、できるだけ「文章」の形で書き出してみるほうが良いでしょう。
主観的な考えは、一つひとつのキーワードとして抜き出してみたときに正しく思えても、伝えたい内容としてはまとまり切っていないこともあるからです。
ステップ②:声に出して読む
文章として書き出せたら、今度は、それを「声に出して」読んでみましょう。
頭の中で「黙読」しておしまいにしてしまう人が多いのですが、実際に「声に出す」音読を強くおすすめします。
音読は、「字を見て認識する」「それを音に変換して発話する」「その音が自分の耳から入ってくる」というプロセスになっています。
その結果、黙読よりも「読みにくい」とか「聞いていて違和感がある」という客観的な気づきを得やすいのです。
また、音読によって、自分が書いた文章ではなく「他人が書いた文章である」と客観的にとらえやすくなり、おかしなポイントにも気づけるようになります。
例えば、最初の文章が「今期はSNS広告に力を入れましたが、売上が伸びなかったため、この施策は失敗です」だったとします。
これを客観的に読むと、「SNS広告と売上の関係性」についての考察が不十分で、何をもって失敗・成功を判断しているのか疑問を感じます。
こうした点に気づき、どのような情報を追加すると話が論理的なものとなるのか、客観的な視点から考えていきます。
ステップ③:自分の言葉として再構成
ステップ②で気づいた、読みにくかったり、聞いていて理解しにくかったりする部分を推敲していきます。
自分の考えが十分にまとまっていない部分が見えてくれば、そこを考え直します。
先ほどの例ですと、
「SNS広告の集客力は期待通りであり、またクリック率も十分に高かったです。ただ、そこから購入に至るCVR(コンバージョンレート)が低かったため売上貢献につながりませんでした。今後は、SNS広告に加えてLP(ランディングページ)や商品説明の改善を検討します」
など、客観的な視点で気がついた「SNS広告と売上の関係性」についての不足を補うための情報を加えた文章に改善していくことになります。
その他にも、
・資料がわかりづらい(主観)→わかりづらさの理由は?(客観)
→ 情報が詰め込まれ過ぎている、数字やデータなどの具体性に乏しいなど
・B案のほうが面白い(主観)→どういう点で比較し、どういうふうに面白いのか?(客観)
→ ユーザー参加型で興味を惹きやすい、いままでのキャンペーンとはターゲット層が異なっていて新しいなど
このように、「主観的情報」に対して、客観的視点でチェックし、足りない情報を追加していきます。
逆に、まわりくどかったり、脱線していたりする箇所があれば、それらはバッサリ削除してみても良いと思います。枝葉を落とすことで、話の純度を上げることができるからです。
こうして、自分の中でまとめ直した文章は「客観性を踏まえた自分の考え」として他人に伝わる状態になっています。
この一連のステップを踏むことで、「自分が何を言いたいのか・伝えたいのか」を相手に伝わる形として明確にすることができるのです。
(本記事は『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』の一部を抜粋・編集したものです)