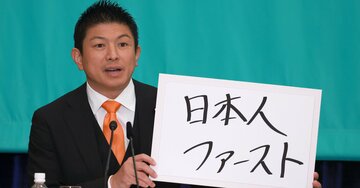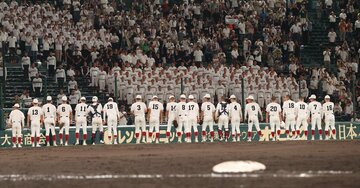有名コンサルの不祥事対応マニュアル
がまったく機能しなかったワケ
吸水シートを油で揚げて客に提供してしまうのも、茶わん蒸しにビニールゴミがついたまま客に提供してしまうのも、洗剤を冷凍庫の上に放置して液漏れさせてアイスのフタに付着させてしまうのも、つきつめていけば現場で働いている人の「危機意識・想像力の欠如」が原因だ。
このような「危機意識・想像力の欠如」というのは時間こそかかるが、現場での教育、さらには研修などによって身についていくものだ。つまり、どんなに「マニュアルを守れ!」としつけたところで得られるものではない。
いや、むしろあまりにもマニュアル、マニュアルとしつこく言うと、事態を悪化させる可能性もある。
厳しい言い方をさせていただくと、異物混入を見過ごしてしまう人は「意識」が低い。「なんかヘンなものを油で揚げているのかも」「茶わん蒸しにヘンなものがくっついてるかも」「洗剤をその辺に放置しておくと食品に付着してとんでもない事故が起きるかも」という、調理人や厨房スタッフならば常日頃から抱いていなければいけない不安や警戒心がないのだ。
では、「はま寿司」の店舗ではなぜそのような不安や警戒心と持たない人がいるのかというと、素晴らしい「マニュアル」があるからだ。
このマニュアルを頭に叩き込んで、マニュアルに沿って仕事をすればいいので、自分の頭で考える必要がない。自分の不注意がどんな深刻な事態を引き起こすのか、という不安を感じたり、警戒心を養ったりする必要がないのである。
なぜ筆者がそう考えるのかというと、危機管理の現場ではそういう問題が非常に多く起きているからだ。
例えば昔、不祥事が発覚した後の対応がメチャクチャで、社会から全方向で叩かれていた某企業から「危機管理マニュアル通りに動いているのになぜか全然うまくいかない」という相談を受けた。聞けば、有名コンサル企業に1000万円近く払って整備したマニュアルだという。
そんな高額なマニュアルがなぜ機能しないのか。現物を読ませていただいて理由がわかった。