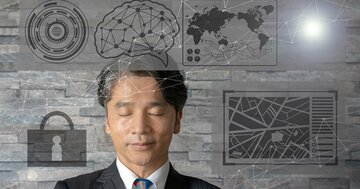表出性言語障害では、まず具体的な名称が言えなくなり、「あれ」とか「こういうやつ」などの抽象的な言い方になっていきます。具体的なものを見せてその名前を答えてもらうテストがありますが、うまくできません。
このように、「言いたい言葉が出てこない」「物の名前を表現できない」ことを「喚語障害」とよびます。
言語障害が進むと
人の顔を認識できなくなる
喚語障害はすべての認知症で認められ、言語障害のなかでは早期から生じます。流暢に話すことが難しくなり、文法の誤りや文章の混乱も生まれてきます。喚語障害の出ている患者には、ゆっくりと落ち着いて、焦らせずに接することが大切です。
受容性言語障害は、側頭葉が侵されたときに目立ってきます。わかったふりをしていても、理解していないことが多くあります。
受容性言語障害が目立つ認知症があります。前頭側頭葉変性症に属する「意味性認知症」とよばれる認知症です。物の名前が言えない、名称を聞いてもその物を理解できないという現象が起こります。たとえば、スプーンと聞いても、何に使うものかがわからなくなります。
症状が進むと意思疎通も難しくなります。よく知っているはずの人の顔を見ても誰かを認識できず、声を聞いても名前を聞いてもわからなくなっていきます。
言語機能の評価は、標準失語症検査などをおこなうと総合的に把握できますが、経験的には患者が嫌がる検査の1つです。できないことを「強制されている」ような感覚になるのだと推測しています。途中で検査を続けることを拒否されることもあり、検査を無理に強行しないほうがいいと考えています。
言語障害のリハビリは、言葉だけに焦点を当てるのではなく、コミュニケーションのリハビリという視点から、ジェスチャーや顔の表情を含めた意思疎通を図ることに目標を置くとスムーズに進みます。
認知症が進むと
計画を立てられなくなる
計画を立てて、それを実行する――仕事であれプライベートなことであれ、日常生活のなかで私たちがいつもおこなっていることです。
家族の誕生日パーティをどうするかといった計画から、夏休みの旅行計画、プロジェクトの進行計画など、大小さまざまな計画があるでしょう。しっかり計画を立てて準備をしなければ、ものごとは失敗してしまいます。