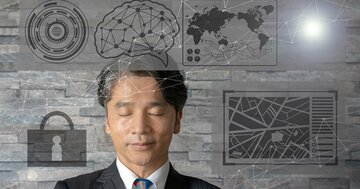このような、「計画を立てて実行する」という人間の営みを「実行機能」(または「遂行機能」)とよびます。実行機能は、記憶や言語にならぶ高次脳機能の1つです。
計画を立てて実行するためには、意思決定、各種の情報収集、間違いに気づいて訂正する、思考の柔軟性などの能力が必要で、じつに多面的な脳の機能に基づいています。
実行機能が成立するためには脳の総合的なはたらきが必要ですが、最も注目されている脳領域は前頭葉の前頭前野です。前頭前野は、判断や思考、意思決定など、的確な知的作業がおこなわれる部位と考えられています。
認知症では、少しずつ、確実に実行機能が障害されていきます。初期には計画を立てる作業に多くの努力が必要となり、疲労感が増します。仕事内容は変わっていないのに「疲れた、疲れた」と繰り返すようすは、後から振り返ると認知症の始まりを示していたと考えられることがあります。
難しい計画の作成では間違いを起こしやすくなります。認知症が進行すると、計画の作成そのものを放棄してしまいます。日常生活に役立つ活動の計画も、他者に頼ってしまう傾向が出てきます。
自販機やATMを
操作できなくなる
自動販売機でペットボトル飲料を買うとき、私たちは目で見て商品の種類や値段を確認し、お金の投入口にお金を入れ、ボタンを押して購入します。目で見た情報が脳の中に入り、確認され、手の動きへと伝えられていきます。
多くの日常動作が、このように「目から入る情報と手の動きの連動」によってスムーズにおこなわれています。服を着替える、顔を洗う、トイレで用を足す、食事をする、バスに乗る……など、すべては知覚情報を脳で判断・確認して、次の動作へと移っていきます。知覚系と運動系が連動し、多くの動作がうまく進んでいます。
目や耳などに異常がなく、手や足の運動能力に異常がなくても、脳における判断や確認がうまくいかないと適切な動作はできません。
プッシュフォンやスマホを操作できなくなる、銀行のATM操作ができなくなる、図形を描き写すことが下手になる、積み木遊びができないなど、さまざまな動作障害が生まれてきます。
知覚情報は入力されても、それが手の運動に連動しない、それが知覚-運動系の障害です。
その病態は、脳内での知覚情報の再構成がしっかりできていないことにあると考えられます。これを「視覚認知障害」あるいは「視空間認知障害」と表現します。