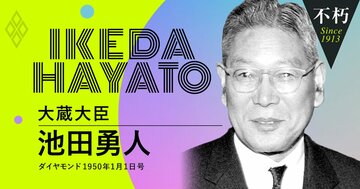第2次世界大戦の終戦間際、東京をはじめ全国の都市は空襲による甚大な被害を受け、「ダイヤモンド」も休刊を余儀なくされた。だが終戦から3カ月後の1945年11月1日、混乱冷めやらぬ中で復刊を果たす。その復刊号から3号連続で掲載されたのが、中野友禮(1887年2月1日~1965年12月10日)の寄稿「これからの事業」(1945年11月1日号、11月11日号、11月21日号)である。
中野は、京都帝国大学理学部で独自の食塩電解法(中野式電解ソーダ法)を開発・特許化し、1920年に日本曹達を創業した化学者であり実業家だ。戦時中は日曹コンツェルンと呼ばれる企業グループを築き上げ、軍需産業を担った人物としても知られる。敗戦直後、経済と社会が瓦解状態にあった日本において、復興に必要な事業とは何かという問いに正面から答えようとした。
本稿で中野が最も力を込めるのは、食糧問題である。戦後の深刻な飢餓に対し、政府は150万町歩の開墾と2000万石の増産を掲げたが、現実にはすきとくわを手にした復員兵士や失業者を動員する「人力頼み」の計画にすぎなかった。これに対し中野は、「法律を作るより田を作れ」「米を食う人間が開墾機械となるのは非効率だ」と痛烈に批判する。
ではどうすべきか。中野の答えは「化学の力」である。ブルドーザーなどによる機械開墾も鉄不足・石炭不足の日本では現実的でない。そこで彼は、戦争で余剰となった火薬やダイナマイトを開墾に転用することを提案する。火薬を用いれば山林や原野を一瞬で耕地化でき、根株の除去から溝渠の掘削まで可能だという。彼は「鎌の代わりに火薬を」と喝破し、原子爆弾が戦争を終わらせたように、火薬を「平和のための食糧増産の立役者」にすべきだと訴える。
同時に中野は、敗戦の本質的原因を「文化と技術の遅れ」に見ていた。米軍のガソリンパイプ敷設やブルドーザーの活用を引き合いに出し、日本の人海戦術との落差を嘆く。「文明程度の低いわが国には受け入れられまい」と自嘲しつつも、化学と産業技術の刷新こそが新日本建設の出発点であると強調する。
もっとも、文中では「砲弾、土地を耕す」として、第一次世界大戦の戦場となったことで山地が平野に変わったフランスのヴェルダンが例示されている。しかし同地は、100年以上がたった今でも銃弾に使われていた鉛や、砲弾に込められていた有毒ガスが土地に残留し、人間はもちろん動物も住めない場所として放置されたままだ。終戦直後の限られた情報の中からの提言であることには留意したい。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
中野は、京都帝国大学理学部で独自の食塩電解法(中野式電解ソーダ法)を開発・特許化し、1920年に日本曹達を創業した化学者であり実業家だ。戦時中は日曹コンツェルンと呼ばれる企業グループを築き上げ、軍需産業を担った人物としても知られる。敗戦直後、経済と社会が瓦解状態にあった日本において、復興に必要な事業とは何かという問いに正面から答えようとした。
本稿で中野が最も力を込めるのは、食糧問題である。戦後の深刻な飢餓に対し、政府は150万町歩の開墾と2000万石の増産を掲げたが、現実にはすきとくわを手にした復員兵士や失業者を動員する「人力頼み」の計画にすぎなかった。これに対し中野は、「法律を作るより田を作れ」「米を食う人間が開墾機械となるのは非効率だ」と痛烈に批判する。
ではどうすべきか。中野の答えは「化学の力」である。ブルドーザーなどによる機械開墾も鉄不足・石炭不足の日本では現実的でない。そこで彼は、戦争で余剰となった火薬やダイナマイトを開墾に転用することを提案する。火薬を用いれば山林や原野を一瞬で耕地化でき、根株の除去から溝渠の掘削まで可能だという。彼は「鎌の代わりに火薬を」と喝破し、原子爆弾が戦争を終わらせたように、火薬を「平和のための食糧増産の立役者」にすべきだと訴える。
同時に中野は、敗戦の本質的原因を「文化と技術の遅れ」に見ていた。米軍のガソリンパイプ敷設やブルドーザーの活用を引き合いに出し、日本の人海戦術との落差を嘆く。「文明程度の低いわが国には受け入れられまい」と自嘲しつつも、化学と産業技術の刷新こそが新日本建設の出発点であると強調する。
もっとも、文中では「砲弾、土地を耕す」として、第一次世界大戦の戦場となったことで山地が平野に変わったフランスのヴェルダンが例示されている。しかし同地は、100年以上がたった今でも銃弾に使われていた鉛や、砲弾に込められていた有毒ガスが土地に残留し、人間はもちろん動物も住めない場所として放置されたままだ。終戦直後の限られた情報の中からの提言であることには留意したい。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
敗戦の理由は頭が古かったから
文化が遅れていたのだ
終戦後、いろいろな人から、これからの事業は何がよいかと問われる。種々議論を闘わせてみた。なかなか尽きない。本誌上を借りて卑見を述べて、大方の叱正を得たい。
私はまず、本当の事業はこれからだと冒頭に一言する。
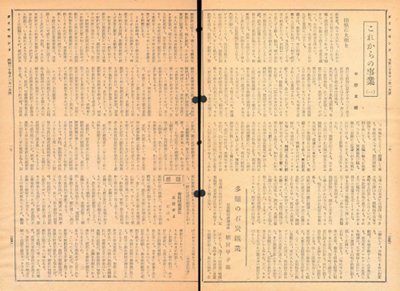 「ダイヤモンド」1945年11月1日号、11月11日号、11月21日号
「ダイヤモンド」1945年11月1日号、11月11日号、11月21日号
われわれは、この数年間、戦に熱中し、勝たんがために全ての物をささげてきた。そして、力及ばずして今日の結果になった。原因は一にして足らずといえども、結局、頭が古かったのだ。文化が遅れていたのだ。
国の発展を武力によるべしとしたところ、武力は武勇にありしとしたところ、皆近代の風潮に遅れていた。
終戦後2カ月、敗戦の自覚がひしひしと身に迫り、ぼうぜん自失しているうちに、食糧問題が深刻となり、内閣が変わった。