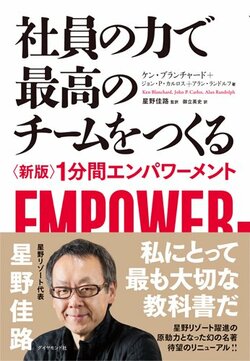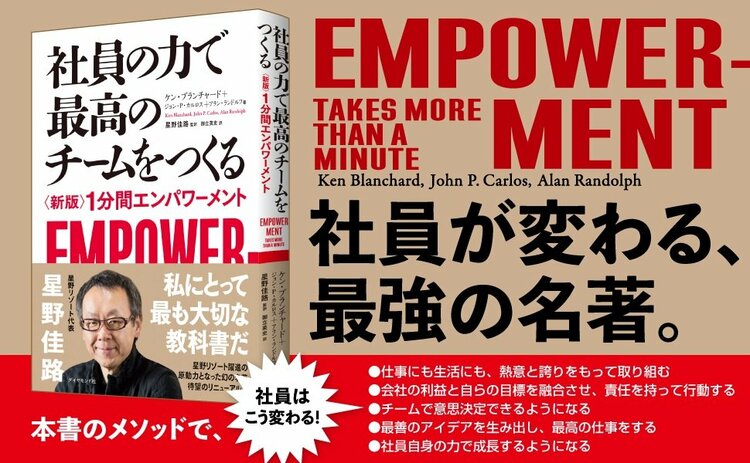低い社員モチベーション、高い離職率、採用難……。今や日本のリゾート業界を牽引する星野リゾートだが、1990年代にはそんな組織の課題に直面していたという。ここから会社を生まれ変わらせたのが、「エンパワーメント」だった。この本がなければ今の会社は存在しなかったと記す星野佳路代表が監訳者を務めるのが、『社員の力で最高のチームをつくる』(ケン・ブランチャード他著)。本書が説く「エンパワーメント」とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
いかにしてエンパワーメントは理解され、実現されたか
社員一人ひとりが高いモチベーションを保ち、自発的にさまざまな行動を起こし、大きな成果を目指そうとする。そんな組織を持つことは、リーダーにとって理想ではないか。
「エンパワーメント」は、自律した社員が自らの力で仕事を進めていける環境をつくろうとする取り組みだ。社員のなかで眠っている能力を引き出し、最大限に活用することを目指している。
エンパワーメントの企業文化が定着すればどうなるか。
本書で紹介されている米国高級食品小売チェーンのトレーダー・ジョーズ社では、従業員と多くの情報を共有し、彼らが自律的に行動できる業務範囲を広げ、責任を重くすることで、26パーセントを超える年間売上増加率を記録したという。
エンパワーメントに取り組んだ8年間で、1店舗当たりの売上を年率10パーセント、店舗数をほぼ100パーセント、総売上を500パーセント以上も引き上げることに成功した。
ただし、エンパワーメントを完全に理解することは難しく、実行はもっと困難だとも本書にはある。だから本書では、会社の経営者マイケルが、エンパワーメントの導入に成功した会社から学びを乞うという物語仕立てになっている。
エンパワーメントを実現するためには、3つの鍵が求められると記す。第1の鍵は、「すべての社員と情報を共有する」だ。主人公マイケルは言う。
しかし、そう考えるなら組織のエンパワーメントはできない、とマイケルは言われてしまう。
相手を信頼していることを示す、いちばんの方法
階層組織特有のマインドセットと思い込みに由来する、そうした時代錯誤の序列意識こそが、まさにエンパワーメントを妨げているというのだ。階層における上位者と下位者のあいだに線を引くような認識は、ビジネス世界ではもはや役に立たない、と。
それどころか、完全に成功の足枷になる。現在、ビジネスの成功はチームとしての努力にかかっている。全社員がしっかり働ける環境を提供できるテクノロジーがある。ところが、人と組織についての間違った思い込みが、それを最大限に活用する道を閉ざしてしまっているというのだ。
もとより、今や誰でもインターネットを使えば、自社の状況に関する情報を入手することができる。マイケルはこう指摘を受ける。
情報共有には勇気がいる。機密性の高い情報ならなおさら。しかし、まわりを見渡して、他社がやりはじめて不安が解消されるのを待っていたのでは手遅れになる。エイヤで実行するしかない。不安解消はあとからついてくる、とマイケルはアドバイスを受ける。
そもそも特定の人間しか知ることが許されていない機密性の高い情報、部外秘情報を設けていることそのものについて、考え直す必要がある。
情報を制限するということ自体が、いろいろなメッセージを相手に伝えてしまうのだ。情報を制限された人は、こう考えかねない。
自分は会社の動きから取り残された、信頼されていない、情報を与えたら悪用すると思われている、情報の意味を理解できないようなバカだと思われている……。自分は信頼されていないと思うのだ。
マイケルはこう聞かされる。
実際、教えを乞うた会社のCEOが業績情報、損益、収益性、顧客逸失コストなどを共有しはじめたとき、社員を信頼しているという強いシグナルが伝わったという。それは、知識と能力を使って会社を成功に導いてほしいというシグナルでもあった。
信頼こそ、エンパワーメントの基礎なのだ。
情報共有は、奇跡を起こす可能性がある
情報共有が何をもたらすのか、わかりやすい例が紹介されている。教えを乞うた会社の人物の友人の話だ。
レストランを経営している友人は、従業員との情報共有がいかに大切かという話をされても取り合おうとしなかったという。情報と従業員の仕事ぶりに関係があるなどと、考えたことがなかったからだ。
その間違った思い込みを改めてもらおうと、ある晩、レストランの閉店後、頼んでスタッフを招集してもらった。接客係の女性、ウェイター、皿洗い、シェフ、そのほか全員が勢揃いした。
テーブルごとにグループに分かれ、次の質問に答えてもらった。
結果は驚くものだった。ばらつきがあったものの、最低が45セント。最高は75セント。1ドルのうち45セントから75セントの儲けが出ると、従業員は考えていたのだ。
実際の儲けは、わずか8セントだった。これをオーナーが伝えると、みんな本当にびっくりしていた。
「私には関係ない、という他人事のような態度になるでしょうね」(P.128)
友人が情報共有の効果を信じるようになったのは、シェフがこう語ったときだった。
「ということは、15ドルで出している原価6ドルのステーキを焦がしてしまったら、その6ドルを取り戻すのに、5枚も売らなければいけないってことですね」
シェフの計算が正しいことを、その場にいたほかのスタッフも確認した。情報を共有したことで、従業員が自分の仕事をビジネスの言葉で考え始めたのだ。
レストランのオーナーは従業員に、「店のバランスシートが読めて、その意味を説明できる人しか、給料はアップしません」と言い渡した。すると、レストランの利益率は開店以来初めて10パーセントを超えた。
オーナーは利益の25パーセントを従業員に還元した。従業員は大喜びで、もっとコストを削減する方法はないか、もっと儲けを増やす方法はないか、いろいろ話し合うようになった。
エンパワーメントの第1の鍵、情報共有は、奇跡を起こす可能性があるのだ。
ブックライター
1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『東京ステーションホテル 100年先のおもてなしへ』(河出書房新社)、『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか』(日経ビジネス人文庫)、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。