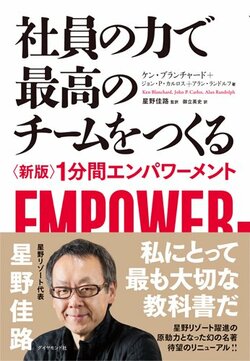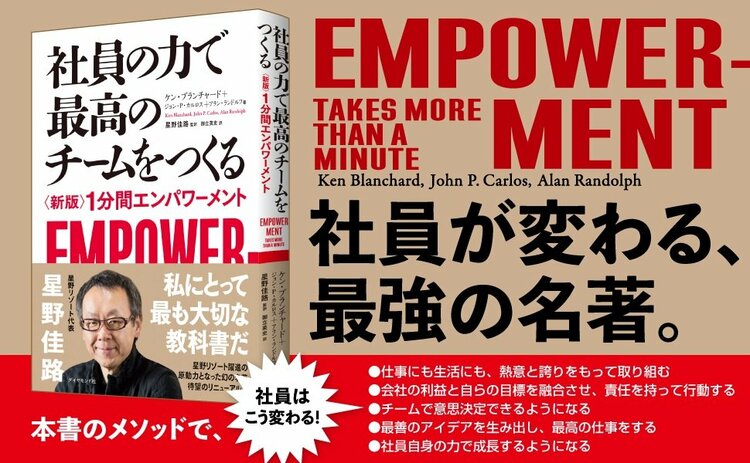低い社員モチベーション、高い離職率、採用難……。今や日本のリゾート業界を牽引する星野リゾートだが、1990年代にはそんな組織の課題に直面していたという。ここから会社を生まれ変わらせたのが、「エンパワーメント」だった。この本がなければ今の会社は存在しなかったと記す星野佳路代表が監訳者を務めるのが、『社員の力で最高のチームをつくる』(ケン・ブランチャード他著)。本書が説く「エンパワーメント」とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
いかにしてエンパワーメントは理解され、実現されたか
社員一人ひとりが高いモチベーションを保ち、自発的にさまざまな行動を起こし、大きな成果を目指そうとする。そんな組織を持つことは、リーダーにとって理想ではないか。
「エンパワーメント」は、自律した社員が自らの力で仕事を進めていける環境をつくろうとする取り組みだ。社員のなかで眠っている能力を引き出し、最大限に活用することを目指している。
エンパワーメントの企業文化が定着すればどうなるか。
本書で紹介されている米国高級食品小売チェーンのトレーダー・ジョーズ社では、従業員と多くの情報を共有し、彼らが自律的に行動できる業務範囲を広げ、責任を重くすることで、26パーセントを超える年間売上増加率を記録したという。
エンパワーメントに取り組んだ8年間で、1店舗当たりの売上を年率10パーセント、店舗数をほぼ100パーセント、総売上を500パーセント以上も引き上げることに成功した。
ただし、エンパワーメントを完全に理解することは難しく、実行はもっと困難だとも本書にはある。だから本書では、会社の経営者マイケルが、エンパワーメントの導入に成功した会社から学びを乞うという物語仕立てになっている。
エンパワーメントを実現するためには、3つの鍵が求められると記す。
第1の鍵「情報共有」、第2の鍵「境界線によって自立した働き方を促す」に続く第3の鍵が「セルフマネジメント・チームを育てる」だ。(第1の鍵に関する記事は『社員と情報共有を「する経営」と「しない経営」…組織に現れる決定的な差とは?』、第2の鍵に関する記事は『リーダーが知りたい「自由放任で成果を出す部下」の育て方』)
主人公マイケルは、顧客の要求に応えられる組織にするべく、階層を減らし、意思決定の権限委譲を進めていた。しかし、うまくはいかなかった。
階層の数が減っても、意思決定がうまく移譲されるわけではない。
エンパワーメント型組織にしたければ、体制や仕組みを根本から変えなければならないのだ。そのキーワードこそが、「セルフマネジメント・チーム」だった。
大きな責任ある仕事もチームならできる
マイケルは、こう説明を受ける。第3の鍵は、階層思考をセルフマネジメント・チームで置き換えるということだ、と。
昔ながらの階層組織のままでは、上が決めたことを下におろす一方通行のコミュニケーションしかない。チームは提案はするものの、それをもとに意思決定するのはマネジャーである。
しかし、今や競争環境は大きく変わっている。組織をスリムにして顧客に近づき、顧客の要求に応えながら、同時に内部統制を効かせて会社の利益も守る必要がある。ところが、階層思考がしみついた組織にはそれはできない。
意思決定するのは上司。動きは遅く、手続きも面倒。そこで、エンパワーされた社員から成るチームで、階層組織でやっていたことの多くをチームでやることにしたというのだ。
「セルフマネジメント・チーム」である。マイケルは、問うた。
「なかなかユニークなチームですよ。業務プロセス全体あるいは製品やサービス全体について責任をもつ社員によって構成され、仕事の最初から最後までを、このチームが計画し、実施し、管理します」(P.102-103)
セルフマネジメント・チームには、管理職が必ずしもいるわけではない。いたとしても、一見しただけでは誰がマネジャーかわからない。全員が等しく責任を分かち持っているからだ。
メンバーが交代でチームリーダーを務めることもあるが、それもチームが決める。話を聞いた人物の部署は重要な使命を担っていた。会社にとっては顧客の動向を察知するセンサーであり、顧客にとっては問題解決の窓口。
会社が行う顧客への対応のどこかに、少しでも間違いがあれば、対外的なものであろうと対内的なものであろうと関与した。
エラーが発生したら、ただちに関係するあらゆる情報を集めて在庫管理と請求の業務に関わる全員と共有し、発生原因の理解と再発防止策を徹底した。これは大きな責任ある仕事ではないか、とマイケルは問うた。
指示はしない。必要な情報だけが示される
顧客に適切なサービスを提供するのは、会社全体の責任だ。顧客サービス部門の各チームは、会社の努力を先導する案内役にすぎない。ポイントは、従来はマネジャーが行なっていたことを、常にチームが行なっているということだ。
社内の情報を集め、分析し、何をすべきかを決め、決めたことを伝える、という仕事がチームに委ねられているのだ。マイケルは自分の感想を伝えた。
教えを乞うた会社が目指していたゴールは、組織のピラミッドを単にフラットにするだけではなく、事業活動に関わる意思決定においては、ピラミッドの上下を逆さまにすることだとマイケルは知った。
社長からの直通電話と、顧客からの直通電話、2つの電話が同時に鳴ったら、さてどちらを先に取るか。多くは社長直通電話だろう。しかし、そこにこそ多くの組織が抱える問題がある。
先に顧客からの直通電話を取っても、誰からも文句を言われない組織にならない限り、ピラミッドを逆さまにすることはできないのだ。
それは私の担当ではない。責任が増えるなら給料も上がって当然だ。そんな声に抗うためにも、意思決定は組織のいちばん下、つまり最前線で行わなくてはならないという信念を貫き続けたのだ。
それをチームに行うようにするために、教えを乞うた会社のCEOが始めたのが「お知らせメモ」だった。経営者や上司が書くメモといえば、これこれをこうしておきなさい、という指図メモがほとんど。ところが「お知らせメモ」には指図がない。
問題点と合理的な解決方法を決めるための必要な情報だけが示されているのだ。
こうしてチームは自ら動き始めていく。
星野リゾートの成功の原動力
本書の「まえがき」と「あとがき」には、星野リゾートの星野佳路代表が、この本の考え方を使って、いかにして会社を変革したかが記されている。
本記事で紹介した「第3の鍵」の実現のために、星野リゾートではこんな取り組みを行ったという。
階層組織をセルフマネジメントチームに置き換えるにあたって、日本の「◯◯部長」のような役職名で名前を呼ぶ文化は障害になる。対等に意見交換ができる環境をつくるために、星野リゾートではこのようなルールをつくったのだ。
また、エンパワーメントに関してこのように述べている。
エンパワーメントへの道は簡単ではない。星野氏も多くの困難を乗り越えて今の星野リゾートの成功を築いた。しかし、星野氏の言うように「想像以上の成果」が待っているのであれば、挑戦してみる価値は十分にあるだろう。
ブックライター
1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『東京ステーションホテル 100年先のおもてなしへ』(河出書房新社)、『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか』(日経ビジネス人文庫)、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。