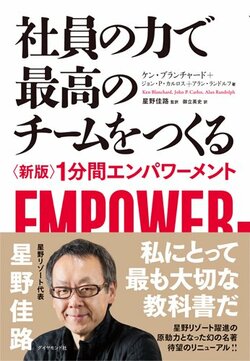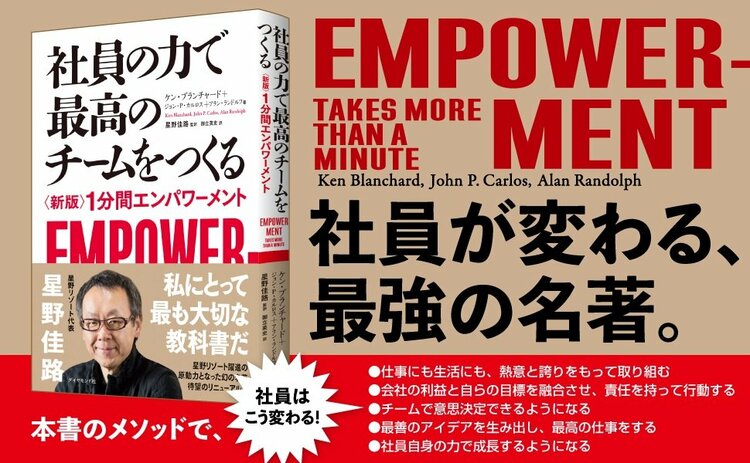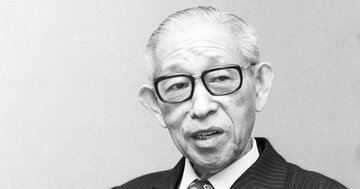低い社員モチベーション、高い離職率、採用難……。今や日本のリゾート業界を牽引する星野リゾートだが、1990年代にはそんな組織の課題に直面していたという。ここから会社を生まれ変わらせたのが、「エンパワーメント」だった。この本がなければ今の会社は存在しなかったと記す星野佳路代表が監訳者を務めるのが、『社員の力で最高のチームをつくる』(ケン・ブランチャード他著)。本書が説く「エンパワーメント」とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
いかにしてエンパワーメントは理解され、実現されたか
社員一人ひとりが高いモチベーションを保ち、自発的にさまざまな行動を起こし、大きな成果を目指そうとする。そんな組織を持つことは、リーダーにとって理想ではないか。
「エンパワーメント」は、自律した社員が自らの力で仕事を進めていける環境をつくろうとする取り組みだ。社員のなかで眠っている能力を引き出し、最大限に活用することを目指している。
エンパワーメントの企業文化が定着すればどうなるか。
本書で紹介されている米国高級食品小売チェーンのトレーダー・ジョーズ社では、従業員と多くの情報を共有し、彼らが自律的に行動できる業務範囲を広げ、責任を重くすることで、26パーセントを超える年間売上増加率を記録したという。
エンパワーメントに取り組んだ8年間で、1店舗当たりの売上を年率10パーセント、店舗数をほぼ100パーセント、総売上を500パーセント以上も引き上げることに成功した。
ただし、エンパワーメントを完全に理解することは難しく、実行はもっと困難だとも本書にはある。だから本書では、会社の経営者マイケルが、エンパワーメントの導入に成功した会社から学びを乞うという物語仕立てになっている。
エンパワーメントを実現するためには、3つの鍵が求められると記す。
第1の鍵「情報共有」(「情報共有」に関する記事は『社員と情報共有を「する経営」と「しない経営」…組織に現れる決定的な差とは?』)に続く第2の鍵は、「境界線によって自律した働き方を促す」だ。
主人公マイケルは、部下をエンパワーするためには、仕事の枠組みやルールは少ないほうがいいと考えていた。
しかし、社員の立場に立ってみたらどうか。自由に働けるというだけでは、混乱しかねないのだ。行動のよすがとなる、何らかの枠組みが必要になるのである。
アップルは、夢物語をまず描いたからこそ
ただ、枠組みといっても、これ以上やってはいけないという禁止を示す境界線のイメージではない。
エンパワーメントの文脈における枠組みというのは、自分たちで決めることができ、決めたことに従って行動して構わないという、「自律を促す境界線」を意味するのだ。
社員はエンパワーメントにおいて、新しい考え方と新しい働き方を学ばなくてはならない。マイケルはこう説明を受ける。
ガイドラインがなければ、社員はエンパワーされる前の古い習慣に戻って、慣れ親しんだ昔の家に帰ってしまいかねない。
境界線にはエネルギーを特定の方向に進ませる力がある。水は土手という境界線があるから、川になっている。なければ、大きな水たまりだ。
境界線とは、エンパワーメントのために、社員のエネルギーを方向づけ、勢いを与えるものなのだ。
こうしてマイケルが受け取ったのは、新しい境界線を定めるときに重要と考えた要素の箇条書きだった。自律した働き方を促進する6つの境界線だ。目的、価値観、イメージ、目標、役割、組織の構造とシステム。マイケルはこう説明される。
簡単に言えば、全社員が思い浮かべる明日の会社の姿のことだ。アップルは創業時、誰もが自分のコンピュータを所有する世界を思い描いた。当時としては夢物語だった。これこそが、ビジョンだ。ビジョンが確立すると、それを達成する手段も明確になる。
そして社員の目標設定を行う際、「あなたが会社から期待されていると思う仕事を10個挙げてください」と書き出してもらっているとマイケルは知る。社員が考えていることと、会社が期待していることには、往々にしてギャップがあるからだ。
自分の役割は何かを本当に理解できているか
部下が自分の仕事だと認識していることと、部下が当然やってくれると上司が期待していることのあいだには、しばしば食い違いがある。
その例が、教えを乞うた会社で話をしてくれた人物の友人で、コンビニエンスストアを経営している夫妻の話として語られる。
ストア経営にとって大事なことがなかなか実施できず、いつも苦労していた。そこで、雇っている従業員に自分の仕事だと認識していることを10個書き出してもらったという。
②レジの現金に過不足がないようにする
③在庫の棚を整理整頓する
④トイレを清潔に保つ
⑤ガソリンタンクに水が混入しないよう点検する
⑥コーヒーをつねに淹れたての状態に保つ
⑦駐車場をきれいな状態に保つ
⑧休憩室を整理整頓する
⑨陳列商品を回転させる
⑩商品を発注する(P.80)
一方で、オーナー夫妻にも、従業員に責任を持ってもらいたい点を10個、書き出してもらった。
②利益
③顧客の評判
④サービスの質
⑤現金管理
⑥店舗の全般的外観
⑦適正在庫
⑧店員教育
⑨施設管理(保守・修繕)
⑩商品ディスプレイ(P.81)
この2つのリストを見比べたことで、オーナー夫妻は何が問題だったかを理解した。間違っていたのは、自分たちだったのだ。
こうして欲しいと指示はしながらも、日々の業務の中で口うるさく言っていたのは、ルーティンな作業レベルだったのだ。相反する2つのメッセージを伝えていたのである。
エンパワーメントにおいては、正確な情報が共有されていない社員は責任ある仕事ができない。加えて、自分のゴールと役割がはっきりわかっていないと、エンパワーされないのだ。
社員は企業のビジョンを共有し、その中で自分の役割は何かを理解し、自分がどんな違いを生み出せるかを自覚したとき、ビジョンは本当の力を発揮するのだ。
ブックライター
1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『東京ステーションホテル 100年先のおもてなしへ』(河出書房新社)、『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか』(日経ビジネス人文庫)、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。