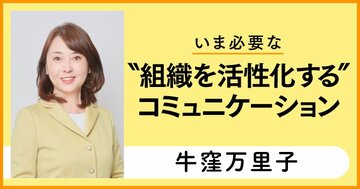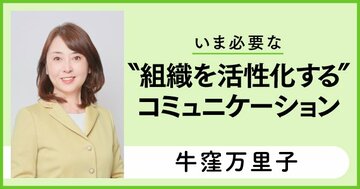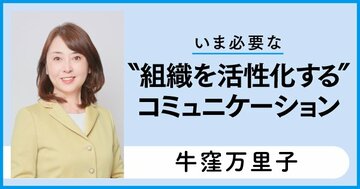質問される側(講師)が実践したい3つのメソッド
一方、質問を受ける立場にも独特のプレッシャーがあります。場を円滑に進めるために、私が実践しているポイントを3つ紹介します。
(1)質問が出ないときの工夫
沈黙が続くと会場の空気は重くなります。そんな時は「今日のお話で、職場ですぐに実践できそうだと思った内容はありますか?」など答えやすい質問を投げかけると、参加者が声を出しやすくなります。または、「今日のご感想でもいいので」と促すと、手を挙げやすい雰囲気になるようです。誰か一人でも手が挙がれば、その方をきっかけに次々と質問が出てくるということも多いです。
(2)的外れな質問への応え方
セミナーのテーマから外れた質問が出ることもあります。その際は、まず、「とてもユニークな視点ですね」と肯定してから、「実は今回のテーマとも関わりがあります」と橋をかけ、本題に戻します。
以前、「職場でのコミュニケーション」をテーマにお話しした後の質問で、「我が家では妻との会話がほとんどなくなり、ギクシャクした状態で、どう解消したら良いものか」という個人的な悩みの質問があり、「まずは家庭内のコミュニケーションが基本となるので、ご夫婦の課題解決から始めましょう」と話題をつなげたところ、会場が笑いに包まれました。そのあとに、「家庭内の会話はまさに身近なコミュニケーションです。一日の終わりに今日いちばん良かったことを必ず聞くようにすると、相手の気持ちが前向きになり、自然と会話が続きます。職場でも同じように“良いこと探し”を取り入れると、社員のモチベーションアップにもつながりますよ」とアドバイスもしっかりと伝え、的外れだった質問から、その日のテーマに引き戻しました。
(3)答えきれない質問の扱い
「大切なテーマなので、今日の時間では触れきれませんが……」と前置きした上で、補足資料を案内するか、後日のメールで回答を提案すると誠実さが伝わります。無理に答え切ろうとして場を混乱させるより、次につなげる姿勢のほうが参加者の信頼を得られます。
以上の3点が、私が実践している主なポイントになります。
質疑応答は、質問者と講師のやりとりにとどまらず、会場全体に学びを広げることが目的になります。そのためにはまず、質問を要約してから答えることです。
これまでの経験から、質問の言葉は省略されて伝えられることが多いため、「今のご質問は、つまり……」と講師が整理してから答えると、他の参加者も理解しやすくなります。また、答えるときは質問者だけでなく、会場全体を見渡しながら話すと、参加者全員が対話に巻き込まれた感覚になります。